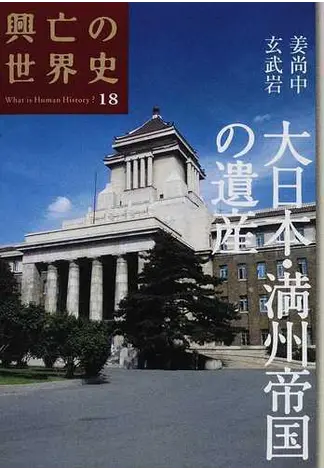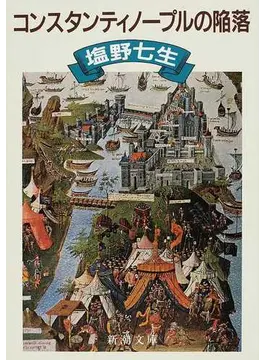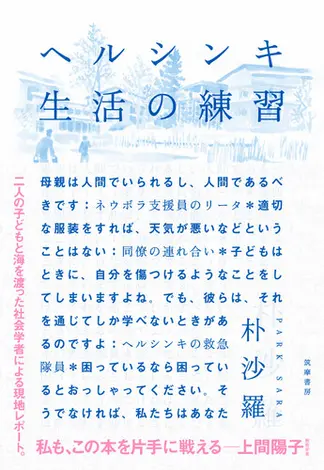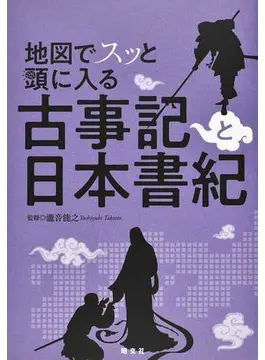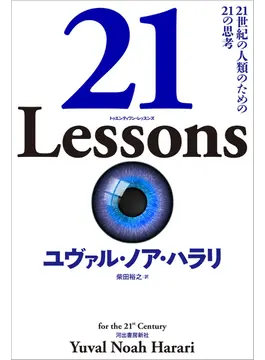私の世代だと”オスマン・トルコ”には馴染みがあるが、”オスマン帝国”という響きには馴染みがない。”トルコ”と付くと見えなくなるものがあると筆者は説く。この国はトルコではなく「何人の国でもない」帝国であり、「イスラム帝国ではない」でもないと。この自称「オスマン家の国」の興亡を描いた書籍である。
「イスタンブールの陥落」を読み終わり、この帝国がコンスタンティノープルを征服し、あのローマ帝国に続くビザンツ帝国の1000年の歴史に終止符を打ったのだ。その時のスルタンであったメフメト2世は五つの言語を操るわずか21歳の青年であった。オスマン帝国がどのように生まれてどのように発展していったのか?その強さに興味が沸々と湧いてきて、本書を手に取った。
本の構成
著者は現在トルコがあるアナトリアの状況から説明を始め、一地方豪族だったオスマン家からメフメト2世の親のムラト2世までどのよう周りの部族を統一していったかを解説する。その後、スルタンによる征服の時代がはじまり、最大の領土を迎えるスレイマン1世の時代まで続く。そこで法や世論についての話を挟み、オスマン官僚による支配の時代への変遷を明らかにしていく。その後、オスマン社会の農民や商人の生態、異教徒たちの生態、女性や詩人などに触れた後に、国際情勢と国内の変遷、さまざまな帝国内の問題と近代国家への対応と限界を描いていく。
帝国の歴史に加えて、その統合の方法と文化や他宗教・女性についても触れていて、オスマン帝国のありようやシステムの変遷がよく理解できた。文化財や資料の写真も随所に折り挟まれ、地図やシステムを説明した図などがありより楽しみながら読み進めることができた。先のメフメト2世に興味があったが、欧州に脅威を与えて知名度の高いスレイマン1世に多くのページが割かれていた。
気になったポイント1 ティマール制の変遷
興味深かったのは国家を統合する仕組みとして在郷騎士たちを取り込むためのティマール制だ。日本の戦国時代に似ている気がするが、領地とそこに紐づく税収を分配して、それと引き換えに領地の管理と軍役を課せられる。しかし時代が進み火器の導入に伴い、在郷騎士の重要度が低下してくる。それと共に徴税請負制が広がり、システマチックに徴税が行われるようになり中央にお金が集まる。戦力も在郷騎士から常備軍に100年かけて徐々に移行していった。また徴税権の売買が起こり、富が偏在していく過程で官僚組織やイエニチェリの弱体化が起こっていった。
筆者はこの徴税システムの移行を、戦費で膨らんだ財政赤字を解消するための「偉業」として、好意的に官僚の見えない手柄と見ている。一方で在郷騎士の力が落ちてくるのは地方の経済力の低下を招き、そこに住む農民などにも文化的経済的な影響があったのではないか?と感じてしまう。現在の日本が抱える富の偏在と、企業という中間組織の力の低下、地方の疲弊などを見ていると他人事ではない。官僚と結びついた大商人(グローバリスト)が国家のシステムを変えていったのではないかと考えてしまう。この自然に生まれてくる富の偏在をどう抑えていくかが国家経営の肝であるように感じる。その辺りは別に勉強を進めたい。
気になったポイント2 「何人の国でもない」オスマン帝国
「イスラム帝国ではない」オスマン帝国についてはイスラム法の中にスルタン法を位置付け、政府・税制・軍・非イスラム教徒の処遇などが明文化されていたと説明されている。もう一つの「何人の国でもない」オスマン帝国だが、章が設けられるわけではなく、大宰相にどのくらい多様性があったのかなど客観的なデータなどは示されていない。一方で人材の登用などは固定的でなく、能力のある人が出世できたというのは理解できた。それが「何人の国でもない」という多様性流動性を支えていたのではないかと感じた。以下は印象的な文章だった。
トルコでは、すべての人がうまれつきもつ転職や人生の幸福の実現を、自分の努力によっている。スルタンの素で最高のポストを得ているものは、しばしば、羊飼いや牧夫の子であったりする。彼らは、その生まれを恥じることなく、むしろ自慢の種にする。祖先や偶然の出自から受け継いだものが少なければ少ないほど、彼らの感じる誇りは大きくなるのである。
p.122 パプスブルグ家のオスマン大使ビュスペックの書簡の一部
最後に
筆者の一番言いたいことはタイトルにある「500年の平和」であるはずである。「『何人の国』でもなかったオスマン帝国のあとには、『民族の時代』が訪れた」とあるが、民族運動の中で統合されていた地域は国民国家として独立し、最後に残ったトルコも国民国家となっていく。この異民族支配から独立を果たした「近代化」の200年の過程でバルカンで流された血はいかほどか。民族単位の国ができあがっているか。バルカンはアナトリアは平和なのか。筆者は民族の時代の中で否定されてきたオスマン帝国時代をバイアスなく位置付けようと本書を締めている。
国民国家の理想に侵されている人にはぜひ読んでほしい。私はトルコ建国の父と呼ばれているケマルアタチュルクを素晴らしい人と見ていたが、どうもそんな簡単なものではないと変化した。最新のオスマン帝国の研究にもぜひ触れてみたいと思う一冊だった。