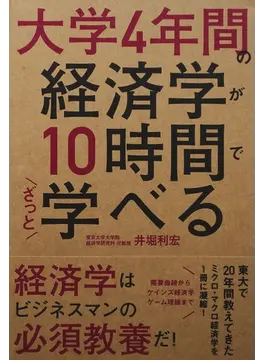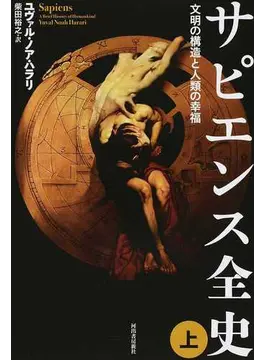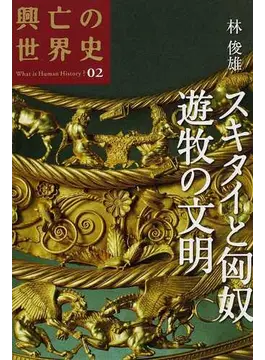
あ
本の構成
「はじめに」では騎馬遊牧民という用語、スキタイ・匈奴を取り上げる意味、二人の歴史家からの視点を説明する。ヘロドトスの歴史と司馬遷の史記、それぞれでスキタイが取り上げられているが似通った特徴があるとのこと。
第一章「騎馬遊牧民の誕生」では主に考古学的な観点から騎馬民族を追っていく。現地の人がヒルギスフール(キルギス=クルグス人の墓)と呼んでいる円形または方形の積石塚と鹿が彫り込まれた石柱である鹿石群からなる遺跡を発掘する。墓は王朝の初期では威光を示すため大きく、のちに小さくなるという。墓であるかどうかについては人骨が出たとのこと、周りの積石塚からはいっしょに葬られたと思われる馬の骨が出ている。大きいヒルギスフールは1367基の積石塚があるものもある。次に動物の家畜化について定住集落と農耕の確立によって生まれたとされる。初めは羊や山羊の食肉から家畜化されたとされている。馬についてはウクライナの前4000年の遺跡から馬の骨が出たので騎乗が行われていたと言う説が出たが、放射性炭素測定からは馬の骨は前800-500年と出て騎乗の年代は大幅に下げれた。
次に遊牧の発生については定住から徐々に集落外へ日帰りで放牧に出かけるようになっていったという説が説明される。農耕牧地は草原地帯の西部には前6世紀に伝わったといわれているが、草原地帯の放牧化は遅れており、前3500年ころにメソポタミアで車が発明されて放牧化を促したとされている。ただしモンゴル北部では車を使わずヤクに荷物を引っ張らせる方式が取られている。また前3000年紀中ごろから気候が徐々に乾燥化してカザフスタンでは半砂漠と草原が形成され、牧畜に適した風土となった。さらに馬車より騎馬の方が早いとされ、メソポタミアを中心とした地域で馬に乗った人物の粘土板などが発見されている。騎乗者は馬の腹に巻いた帯を持ち馬の尻にまたがっている。これは骨があるのでロバの乗り方で乗ったとされている。とこれは広く普及することがなく前2000年紀の初めにスポーク付き車輪の二輪車が登場する。銜(くつわ)とその留め具は草原地帯で発明された可能性がある。西アジアや地中海では全十四世紀後半には銜につけた手綱をもつ騎乗者の浮き彫りがあるが、ロバ式騎乗ではある。前10世紀に入ると西アジアや地中海世界で牙を表現した資料が急増する。草原地帯では前九〜前八世紀になると騎馬関係の証拠が増え始める。これがスキタイ文化の始まりである。一つは世界的な気候変動が乾燥期から湿潤期の威光期、半砂漠だったところが草原に変わり始めている。
第二章「スキタイの起源」ではスキタイ以前や以後の集団の動きを分析する。まずは語り継がれているヘロドトスやギリシア人による二説を取り上げている。二説は外来の神と地元の神の交わりに起源をもち末っ子が王族になったとしている。さらにヘロドトスが語る農民スキタイや農耕スキタイについて分析する。さらにヘロドトスが最もらしいと語る第三説ではスキタイは初めアジアの遊牧民であったが別の騎馬遊牧民に攻められかなり東の方から移動してキンメリオイを追い出し北カフカス・黒海北岸の草原に現れたという。スキタイ外来説は以前はマイナーな説だったがそれを裏付けるアルジャン古墳が見つかり今では内陸アジア説が有力とされている。アルジャン古墳からは銜も見つかったが炭素14年代測定法では前9から前8世紀の先スキタイ時代と出た。ヘロドトスによると黒海北岸にスキタイが現れる前にはキンメリオイがいたはずである。キンメリオイがスキタイに銜(くつわ)をもたらしたのではないか。ヘロドトスによるとキンメリオイはスキタイが迫り一部がシノベのある半島に逃げたとされる。アッシリアの資料ではギミッラーヤやイシュクザーヤの名前でキンメリオイやスキタイが出てくる。キンメリヤは前640年ごろアッシリアに敗れ、前七世紀ごろリュディアにも敗れ姿を消す。スキタイはアッシリアの資料では同盟関係を結んでいた。ヘロドトスによるとアッシリアの首都が包囲された時にスキタイ軍が救い出しが、その後アッシリアはメディアと新バビロニアの連合軍に負けてアッシリア帝国は滅亡する。またスキタイが28年間アジアを支配したとあるが時期は定かでない。メディア王キャクサレスがスキタイを宴に招いて酒に酔わせた大部分を殺してしまった。生き残ったスキタイは故郷にもどったとされるが北カフカスが黒海北岸が濃厚である。また彼の治世に本国から反乱を起こしてメディアに庇護を求めてきたスキタイがいたが当初は信頼していたが一度彼がキレてしまったのが原因でスキタイがリュディアに移動し、リュディアが引き渡しに応じなかったので、メディアとリュディアの間で戦争になった。スキタイがキンメリオイを追って西アジアに現れたというヘロドトスの記述を信じる人は現在ではいない。またギリシアの資料では略奪を目的に侵入してきたとあるが傭兵として雇われていた可能性もある。考古学資料では先スキタイ時代の武器や馬具がアナトリア中部や東部の遺跡で見つかっている。また先スキタイから初期スキタイまでの遺物はアナトリアやカフカス南部で続々と見つかっている。これらの資料からは北カフカス・黒海北岸の部族がカフカス南部とアナトリアに移動していることを示している。
第三章「動物文様と黄金の美術」では遺跡から出土する遺物の特徴からスキタイ文化を見ていく。スキタイ文化を特徴づけるものは動物文様、馬具、武器である。武器は伝播しやすいが文様は伝播しにくい。元々はスキタイが西アジアを28年支配したという記述もあり”蛮族”も美術に目覚めたという説が有力だったが、南シベリアの一角にはやくも初期の動物文様が現れていることからスキタイ東方起源説が一気に有利な方に傾いた。一方で古墳から出土したものも西アジアのものもある。金製装飾が施されているアキナケスの剣と木製鞘などは鹿の表現をつぶさにみていくとスキタイのものと異なっていたり、複数の文化が混ざっているのが分かる。次は初期スキタイの美術を見ていく。東部の草原地帯では盗掘は稀だったがロシア人が来てから毎年のように行われていた。これらの遺物に文化的な価値を見出したのはオランダ人の学者ヴィトセンだった。彼はモスクワに一年滞在し地理、民族、言語などの資料を集めオランダに帰ってからも資料を集め続け大著『北東タルタリア』を著した。ピョートル1世はシベリア出土の金銀に美術的な価値を認識して金製品を集めるよう命令したり個人売買を禁止したりした。この時に集められた完成品はエルミタール美術館の黄金の間に展示されている。カザフスタンの東部にも重要な初期スキタイ時代の遺跡がある。1971年頃にアルジャン古墳が調査されて学会に激震をもたらせたが、その30年後にアルジャン二号墳で盗掘を免れた金製品が5700点も発見された。初期スキタイ時代のモチーフのつま先だった鹿や脚を折りたたんだヤギの動物文様の短剣などが見つかっている。出土品全体からは西アジアやギリシアのモチーフがまったく見られない。石室のカラ松から前619年〜608年の範囲ものとされる。鉄製品は前5世紀にならないと現れないというスキタイ東方起源説の弱点を解消すると共に、スキタイ美術の東方起源説がますます有利になった。次は後期スキタイの美術である。後期になると動物文様が写実的になり植物文様もみられる。ギリシア風からの影響がみられギリシア風スキタイ美術と呼ばれる。これらの作品は黒海北岸のギリシア人植民都市に住んでいたギリシア職人が作ったと考えられている。黒海北岸で見つかった金の胸飾りの文様では動物闘争文や花とつる草の文様がみられ、さらに搾乳風景などスキタイの日常生活が描かれている。
前六世紀後半にイラン高原に起こったアカイメネス朝がアッシリアをしのぐ大帝国を建設した。アカイメネス朝は西方へ進出してギリシア諸都市と衝突もしていたが東方へも遠征を行い、中央アジアの草原でサカと総称される騎馬遊牧民と接触することとなった。イラン西北部の碑文によるとサカには尖り帽子のサカと呼ばれた人々もいた。またヘロドトスはサカをサカイと表記し、クセルクセス一世のギリシア遠征に参加した一部隊として尖り帽子のサカイについて言及してペルシア人はスキタイをサカイと読んでいると書いている。全体をサカ文化と呼んでもよいが中央アジアの騎馬遊牧民についてだけサカの名称が適用されている。この中央アジアのサカの初期の美術はピョートルのシベリアコレクションの大部分も含まれる。後期のサカ美術ではイッシク古墳の出土品がある。発見された以外は金ずくめで尖り帽子、上着、ベルト、ブーツ、剣と鞘などは金細工で飾り立てられ、黄金人間としょうされるようになった。特に注目されたのは尖り帽子であった。尖り帽子といえば尖り帽子のサカであったので、本拠地はこの遺跡のあるカザフスタン南部であるという研究者もいるが、尖り帽子ははるか西のクリミアのクル=オバ古墳のツボにも表現されており、カザフスタン南部に限定されるものではない。筆者は動物文様に注目し初期スキタイの変形とみなすことができ、また体をひねった動物表現がみられることに注目する。またアルタイは金山でもあるが重要なパジリク古墳群がある。1929年に一号墳が発掘された盗掘はうけていたが盗掘の穴から雨水が流れ込み墓室の底は水浸しになった。木や皮革、繊維製品などの有機質の遺物がよく残る条件の一つは水に浸かって空気にふれないことである。アルタイは冬が長く8月末には雪が降り始め真冬にはマイナス40度まで下がる。墓室内の水は凍結する。しかし翌年の夏になっても氷は溶けなかった。いつの間にか盗掘坑もふさがる。夏には雨水が浸水したが氷を大きくし地下墓室には巨大な氷が形成され、有機質の遺物は水浸しよりもさらに条件の良い冷凍の状態で保存された。バジリクでは大型古墳も発掘されたが、すべて凍結古墳であった。そこから木製の馬車、革製の鞍、色鮮やかな馬具装飾、ペルシア風絨毯、巨大なフェルトの壁掛け、馬の痛い、刺青された人間の皮膚など貴重な遺物が次々と出土した。その後1991年にアルタイのウコク高原で凍結古墳の再発見に挑んだが氷はほとんど溶けており遺骸は朽ち果てていた。そのごアルタイ高地で女性と男性の凍結墓が見つかり、モンゴル領内でもやや溶けかかっている凍結墓を発見して髪がブロンドの男性が発見されている。アルタイのスキタイ時代後期の文化は古墳群からとったパジリク文化と呼ばれている。高品質の絨毯も出土されているがペルセポリスの浮き彫りと構図がまったくおなじなのでペルシア産とされている。しかし文様帯にはヘラジカが描かれているがペルシアにはいないので本当にペルシアさんかどうかはかなり疑わしくアルタイ産の可能性が高いと見る。最後にフェルト製鞍覆いにあるグリフォンの尻の文様に見られるギリシアの影響はどこから来たのかを分析する。ギリシア人植民地の黒海北岸から草原地帯を進みアルタイに至るルートが考えられる。北京とローマを結ぶ最短ルートを地球儀上でみるとほとんどが草原地帯で超え難い大山脈もなければ砂漠もない。またその途中にアルタイがある。オアシスルートの200~300年前に草原ルートのシルクロードが開かれていた。
第四章「草原の古墳時代」では先スキタイ時代から後期スキタイ時代までの主だった古墳を分析していく。まずはスキタイ文化が栄えた前8世紀から前7世紀にかけての他のユーラシア大陸の西部の金属工芸美術をもつ文化をみていく。ケルト人が残したハルシュタット文化、イタリア半島中部のエトルリア文化、バルカン半島のトラキア文化とダキア文化、アナトリアのリュディア王国とフリュギア王国、アッシリアの影響があったウラルトゥ王国などである。美術様式遺骸にも円墳を築く共通点がある。エトルリア、トラキア、リュディアと終末期のスキタイは墓室が切石造りであるがギリシア文化の影響と思われる。古いハルシュタットと初期スキタイ、フリュギアの墳墓では石室が木槨であり、馬の埋葬を伴う点で共通している。さらにハルシュタットとスキタイでは円墳の周りに石囲いをめぐらし、墳頂に石人をたてることもあった。そのため墳墓は起源的にかんけいがあるのではないか、スキタイ墳墓が影響を与えたのではないかとする説もある。スキタイ世界では前9世紀末から前8世紀初頭の王と王妃が埋葬されていたアルジャン一号墳がありこれより古い古墳は見つかっていないが、積石塚で井形に組んだ丸太の中央に墓室があり、墳丘の外に二重三重の小石堆がめぐっている。アルジャン二号墳でも多数の金製品をまとった男女と殉死者や馬が埋葬されていたので王と王妃の墓と言えるが同じような構造になっている。この後初期スキタイの古墳を草原地帯の東から西に見ると木槨墓室を地上か浅い穴の中に設ける王墓が流行していたと結論付ける。
後期スキタイの古墳について分析する。まずはヘロドトスが記録した王族の埋葬や葬儀の方法についてさらう。黒海北岸では高さ14メートルの最大級の古墳が6基発掘されている。そのうちの芝土レンガを使っているチョルトムリク古墳の構造を見てヘロドトスの記述と比べる。この遺跡は前四世紀ごろのものだが、そのころにアタイアスというスキタイ王がいたことが知られているが、チョルトムリクがアタイアスのものだと考える研究者も多い。アルタイのパジリク古墳では有機物が残っていたためにヘロドトスの記述にあるミイラかの手順などが確認され、五号墳から出た四輪馬車も出土してヘロドトスの記述を通りであった。また王権の象徴としてスキタイ古墳に伴って発見される石人について触れる。アルタイから西に2500キロほどにある古墳から出土される石人は三番目の鹿石と特徴が似ているので西方の鹿石と呼ばれることがあり先スキタイ時代のものである。スキタイ時代になると人間の顔がはっきりと書かれた石人が古墳の中や周囲で発見される。後期になると武器や衣服などの表現がやや写実的になってくる。西方の鹿石と石人は共通点があり石人の起源は西方の鹿石とする説が有力だが定かではない。
前四世紀の初めにカザフスタンから西に移動してウラル山脈南部に本拠を置いた部族集団が徐々に強大になり、スキタイを圧迫し始めた。以前は南ウラルにはサウロマタイと呼ばれる人がいたが、東方から移動してきた集団はサウロマタイと合流しサルマタイと呼ばれることになる。バシュコルトスタン共和国でサルマタイ時代の大型の古墳が見つかっている。サルマタイは紀元前四世紀後半にフン族が来襲するまでカスピ海北方から黒海北岸までの草原地帯を支配した。
第五章「モンゴル高原の新興勢力」では匈奴の出現を遺跡と史記から見ていく。まずは匈奴の起源を司馬遷の史記には李牧の匈奴の侵入に悩まされる逸話に匈奴は初めて登場する。その後に匈奴は秦に一時押されるが始皇帝がなくなると元に戻る。また遺跡から出土する遺品をみると中国北方の前四〜前三世紀の中国騎馬遊牧民の文化はユーラシア草原と繋がっていることが確認できる。匈奴の冒頓は単干になり東胡征服する。月氏は匈奴に攻撃され西に移動し大月氏と呼ばれる。大月氏はバクトリアに侵入しローマの資料にも記録され、世界史上初めて東西が同じ出来事を記録する。月氏の領域について議論があるが考古学の観点からはパジリク古墳群は月氏のものではないかという説がある。またパジリクから南へ900キロ離れているスバシ遺跡は同じようなスキタイ文化が見られる。冒頓と劉邦は戦うが最終的には和親条約により漢を事実上支配下に起き、匈奴遊牧帝国が出現する。毎年の貢物と公主の降嫁を続けたが侵寇は止むことはなく漢を悩ませる。
第六章「司馬遷の描く匈奴像」では匈奴の風俗習慣、経済、社会構造を紐解く。まずは天を重んじる文化、二十四長と十進法に基づく軍事組織、南を向いて東にいる左賢王と西にいる右賢王、刑法と暦などを見ていく。冒頓がなくなると子が継ぎ老上単干と名乗る。漢の文帝は新単干に公女に見立てた劉氏の子女を嫁がせる際に中行説と遣わすが匈奴に忠誠を誓って管理の手法などを教示する。匈奴は幼少期から訓練をつんで国民皆兵制度を施行していたので人口が漢の一群以下でも軍事的に対抗できた。また寡婦となった兄嫁を娶る習慣は他の地域でもみられるが軍事体制を優先する騎馬遊牧社会特有の合理性が見られる。中行説は単干に中国に侵入する際に有利な地点と探らせていたとされるが、前169年に14万騎という大軍で現在の甘粛省中心部に侵入した。その後長安から80キロしか離れていない甘泉宮に至り、単干は一ヶ月ほどとどまるが14万騎と10万の兵が戦闘することはなく戻っていった。これは漢の反乱分子が匈奴に援助を求めたものと考えられる。前166年以降毎年毎年匈奴は人と家畜を殺略したので再度和親条約が確認された。その後の恵帝でも同じように和親条約が結ばれた。
前141年に武帝も和親条約を結ぶが月氏が匈奴に敵対心を持っていることを知り月氏と共に攻勢に出ようとする。月氏と連絡をとるために張騫が選ばれ出発したがすぐに匈奴に捕まり単干のもとに連れて行かれ妻も娶らされそこで10年の月日を過ごす。ついに脱出の機会に恵まれ部下と共に月氏に逃亡し、中央アジアに栄える大宛にたどり着く。大宛王は張騫を厚遇し、通訳を付けて大月まで送り届ける。大月は匈奴に王を殺されていて王か女王が立っていたが、漢との同盟には積極的ではなかった。張騫は1年の滞在後、南のルートで帰還するがまたしても捕まってしまう。1年余勾留されるが軍臣単干が他界し後継者争いが起こるさなかにまた部下と匈奴の妻と漢に逃れる。この際に張騫は漢に中央アジアの様々な情報を持ち帰り、次に烏孫との同盟を進言し自らその任に当たる。武帝は一方で張騫の出張後に匈奴おびき出し作戦をするが失敗する。その後正攻法で武将に騎兵を与えて何度か攻めさせるが一進一退を繰り返す。前126年に軍臣単干が高いすると形勢は漢に傾いていく。その後も互いの攻撃は続くが次第に匈奴の有力者が漢に降伏することが増えてきて、匈奴の劣勢がはっきりとしてくる。前119年春に漢軍は総攻撃をかけて一時単干が行方不明になるような自体になり匈奴と漢の両軍に多大な被害が出たが、漢は黄河の北まで領土を広げた。
第七章「匈奴の衰退と分裂」では漢との関係や干ばつや継承問題で分裂する匈奴を描く。前119年の漢の総攻撃の後、武帝の息子の死と財政難から大規模な攻撃ができなかった。これ以降は匈奴に従属している西域や烏孫を匈奴から引き離すことを目指した。この西方作戦を進言した張騫は自ら烏孫に向かったが成果を得ることはできず帰国後に亡くなる。しかし烏孫から漢に連れてきた使者たちが漢の国力を理解すると漢からの公主を娶った。また張騫が西方に放った使者たちが答礼使節を伴って帰国し漢と国交を結んだ。そして中央アジアのほとんどの国が国交を結ぶことになった。また漢は張掖郡と敦煌郡を結ぶ河西廻廊を確保し西方とのやり取りを活発化させると共に匈奴が南の国と連絡が取れなくなった。西方には良馬や珍奇なものがあると聞き武帝は西方にしきりに黄金と絹を持たせた使者を派遣した。基本的に西域では匈奴の使者に比べて漢の使者は軽んじられた。大宛は善馬を多くもっていたが漢には渡さなかったため、李広利を派遣し最終的には善馬を手に入れられるも一度目は途中の西域諸国の協力が得られず引き返す自体にもなった。匈奴の西域支配では駅伝制のようなものや支配国の王子を人質と出させたりしていた。車師は天山の南北にまたがった戦略上重要な国だったが、漢は楼蘭に車師を攻めさせた時は匈奴の右賢王が救援に来たために漢は引き下がった。再度西域六カ国の兵を率いて車師を打たせてやっと降伏させた。その後漢に服従したり匈奴に服従したり行ったり来たりした。
何人かの単干を経て且鞮侯になったときには親漢的な振る舞いを見せて捕虜などを開放したが、また漢の大攻勢が始まる。前99年に李広利が3万騎で天山の右賢王を撃つが敗れる。この頃に小説になっている李陵も匈奴とぶつかり捕虜になり以降は匈奴の右校王という地位で戦う。李広利はこの後に何度か匈奴と戦うが李広利の妻が起こした問題で功を焦り大敗し匈奴に投降する。狐鹿姑単于が他界すると単于継承で問題が起こり単于の求心力が低下した。前71年には漢と烏孫が共同で匈奴に攻勢をかけられ大ダメージを受け、単于は烏孫に報復を試みるが大雪などで逆に大きなダメージを受ける。この苦境にさらに烏孫・丁零・烏桓などの攻撃を受け弱体化する。さらに西域諸国と漢が共同して匈奴側についていた車師を攻撃し制圧する。虚閭権渠単于の後にたった握衍朐鞮単于は国内では残忍にふるまったために離反が相次ぎ自害させられる。その後単于が乱立し内戦になり最終的には郅支単于が勝ち、破れた呼韓邪は南下して漢の臣下となって逃れる。郅支単于は漢とは国交を絶ち烏孫に対抗するため康居と近づく。康居は烏孫王がいる天山西部の赤谷城を襲撃し勝利するが郅支を軽んずるようになったために、郅支は康居を制圧してタラス側のほとりに城を作らせた。郅支が力を付けたのを心配し漢の西域都護府の陳湯が郅支の城を攻めて滅ぼした。
南下した呼韓邪は漢と親和的に接し栄えていく。しかし王莽が実権を握ると亡命者の投降をやめるように要求したり名を漢字一字にするように要求したりと締め付けがきつくなり、王莽が新を立てると不満がさらに強くなり両者は決裂する。王莽は殺され更始帝が漢を再興したが、呼都而尸道皋若鞮単于は盧芳を担いで漢に侵入した。呼都而尸道皋若鞮の後にまた継承問題で南北に分裂し、北匈奴はバイカル湖などの西域まで進出する。
第八章「考古学からみた匈奴時代」では、、、匈奴の王の埋葬については史記に簡素に書かれている。ノヨンオール遺跡は方墳だが墓坑は9メートルある。出土品には動物文様が施されている絹織物もあったが、紀年銘のあるものがあり東匈奴が漢から受け取っていた贈り物が支配者層にも回っていたことが考えられる。その後殉死者をともなうイリモヴァヤバチ遺跡などが紹介される。これらの遺跡と史記の記述を比較して、これらが単干の墓であったか分析する。山中に目立たないように作られているので王の墓といえるが前一世紀から後一世紀のものばかりで前二世紀の匈奴の最盛期の王墳はまだ見つかっていない。
継ぎに定住があったからを見ていく。遊牧は生産性が低いことが知られている。漢書の中にも農耕が行われていたとみられる記述がある。また誰が行っていたかについてを分析する。漢書や史記には匈奴の襲来によって金銀が奪われたという記述はなく人と家畜であったことから、この人たちが農耕に従事させられていたと考えられる。また匈奴に一族と亡命したものもあったが民衆でも匈奴に行くものがあった。モンゴル高原の北側では定住の集落が20箇所ほど見つかっている。イヴォルガ城塞集落が代表的だが四方が土塁に囲まれている。出土品の分析ではほとんどの土器が漢代のものであったり鋤や鍬などの鉄製農具も中国のものと類似していたことが注目される。結論としては漢人が農耕と手工業に従事し、匈奴人兵士が護衛と監視を担っていたと考えられる。
また南シベリアでみつかった中国風の宮殿から中国文化の広がりについて分析する。李陵の宮殿とされていたがそれは否定されて、年代を考えると王昭君が考えられる。ウイグル自治区にある遺跡の出土品からはサルマタイや漢や匈奴など広い地域から影響されていることが見て取れる。アフガニスタン北部の遺跡からの出土品からも漢、インド、ギリシア、サルマタイなどの影響が見られ、各文化が国際的だったことが伺われる。
第九章「フン族は匈奴の末裔か?」では、、、、18世紀中頃にフランスの歴史家J・ドギーニュにより発表されたフン族を匈奴とみなす説はその後に賛否両論がかわされてきた。後漢書では北匈奴と後漢の間で車師とその周辺地域をめぐっての攻防が繰り広げられ、151年に後漢が伊吾に派兵に呼衍王は去っていったという記述を最後に後漢の記録から姿を消す。魏書の西域伝に91年頃北匈奴の単于が後漢と南匈奴の連合軍に敗れた後なら逃走したたする記事がある。この年代を150年代まで下げて後漢の記録と結びつける考え方もある。この説は東胡の末裔と言われる鮮卑の指導者が150年代にモンゴル高原東部に勢力を確立して烏孫にまでその支配を及ぼしたことに裏付けられる。北史の西域伝にも奄蔡と一緒に匈奴が出てくる。ただソクドの国がかつての奄蔡と書いてあり混乱を招いている。後漢書の記述には奄蔡国が阿蘭聊国に改名したとあり、西方の資料ではサルマタイの東部で遊牧部族集団が覇権をとったという記述がある。
その後376年に黒海西北岸にいた西ゴート族が東方から現れた強力な騎馬集団に打ち破られローマとの国境まで逃げてきたのである。四世紀の後半の西方の歴史家によるとフン族はヴォルガ川を超えてアランに襲いかかったようである。375年かその前にはフン族は東ゴートに襲いかかったようだが、東ゴードは別のフンを傭兵に雇ったとある。それでもフンは東ゴートを破り西ゴートに襲いかかる。西ゴートの一部はハンガリーに逃げるがローマに庇護を求めるが、トラキアの将軍が食料を十分に渡さなかったため飢饉が起こり反乱になる。東の皇帝ヴァレンスは援軍を待たずにトラキアでゴートと会戦をするがゴート軍の一方的な勝利となる。このゴート軍にはフンとアランが参戦してたようで、続く2年間はバルカンを荒らし回るが、フンは北方に帰っていったとみられる。395年にはフンの大軍がドン川やカフカス山脈を超えてアルメニア、ローマの属州、ペルシアまで侵入した。侵入の目的は人と家畜だった。
この後、フン族の文化や馬に乗った生活、多色装飾様式と呼ばれた金製品の美術が紹介される。また鞍と鐙の発展の分析に続き、フン型の鍑(ふく、儀式用の釜)の出土の分布とその起源を分析する。
400年ごろフンのウルディンという指導者がトラキアを攻めた。422年にはルアという指導者がコンスタンティノープルまで迫ったので東ローマは和平条約を結んだ。あとを継いだのはブレダ(兄)とアッティラ(弟)だが共同統治はうまく行かず、弟が兄を殺しアッティラだけの体制になる。アッティラは東ローマと交渉し毎年の支払いを倍増させた。その後アッティラはガリアに侵入しそこにいた西ゴードと西ローマと激突し、激戦を戦い双方とも大損害をだしアッティラは本拠地のハンガリーに帰っていく。アッティラはある朝に血だらけで死んでいた。その後フンは急速に衰退していく。フンが国家だったかは定かではないが、フン族の侵入が西ゴードの移動を促し西ローマ帝国を倒壊させたことは事実である。
気になったポイント
ドイツ語のブルグ、英語のバラ、フランス語のブール、スラブ語のグラードは城壁を示しているというのは興味深かった。障壁の文化圏の広がりが言語で表されている。
西アジアに侵入したスキタイがアッシリアなどの傭兵となっていたというのは少し気になった。ギリシア人などが傭兵として雇われていたがどういう条件で傭兵となるのだろうと思う。人口増加などだろうか?とすると生産性が高い国家だったのかとも思う。
スキタイと同時代の文化の紹介でエトルリア文化が出てきた。ローマにも多大な影響を与えたエトルリア人だと思うが、言語系統不明というのは知らなかった。非常に長い文化的蓄積があったのだろうと思う。
サウロマタイの辺りでヘロドトスが女性だけの戦士集団であるアマゾンの伝説は興味深い。スキタイが若い男を差し出して一緒に生活するようになって、その子孫がサウロマタイになったというのは何か民族を超えたつながりを感じて夢がある。
匈奴の墓が見つからないということに関して、森の中に盛り土がない墓ということでかなり見つかりにくいものだと思う。まだ誰も見つかっていないものがあると思うと、早く見つけないとくちてしまうと心配になる。人工衛星などで探すことはできないのか、と考える。
匈奴と中国の人的交流や匈奴よる人の略奪に関連し、自分で匈奴に亡命する農民もいたとあったが、長城は長城の中にいる農民を外に逃げないようにしているという意味もあったのではと思う。日本は海に囲まれているが、陸続きだと外の国に逃げる人たちもいたのだと思う。
最後に
スキタイも匈奴も中央アジアの文明が中国やヨーロッパに与えた影響は多大だし過小評価されていると思う。モンゴル人もテュルク系の国々も今は中国の参加にいるような状態で世界の中ではぱっとしない。これからまた時代が変わってきてまた活躍してくるのかもしれない。とにかくスキタイや匈奴など中央アジアの文化や影響を知りたい人にはおすすめです!匈奴はフンです。