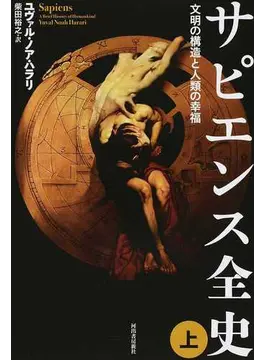
オクスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して博士号を取得し、エレサレムのヘブライ大学で歴史学を教えているユヴァル・ノア・ハラリ氏の著作。流行っているので読んでみたが、著者の多岐にわたる知識が散りばめられた非常に面白い歴史の分析でだった。
本の構成
第一部ではサピエンスが7万年前に認知革命によって架空の伝説、神話、神々を語ることで多くの人が共同作業できるようになったと論じ、第二部では1万に千年前に起こった農業革命によって大量の数字データを処理するために書記体系=文字を作るようになったとなったと分析する。第三部では貨幣・帝国・宗教による人類の統一を論じる。第四部では500年前に始まった科学革命によって神となったサピエンスを語り、サピエンスがサピエンスでなくなる未来を眺望する。
ポイント ー 第一部:認知革命
200万年前に太古の人類であるアウストラロピテクス属はアフリカ・ヨーロッパ・アジアに広がった。そこから分化したネアンデルタール人やホモ・エレクトスは200万年近く生き延びた。何種類かの人類が一万年前まで生きていた。私達は大きな脳、道具の使用、優れた学習能力、複雑な社会構造というような大きな強みを使って史上最強の動物になったと思いこんでいる。しかし人類は200万年間に渡り弱い存在で、他の動物がとった獲物の骨から髄液を吸って生きてきた。人類は30万年前には火を使った調理によって消化しやすくなり腸を短くしてエネルギーを節約し、その分のエネルギーを脳に費やすことができ、現在は25%ものエネルギーを脳に消費している。1万年前までいたサピエンスの兄弟たちはどこにいったのか?従来は交代説と交雑説があり従来は交代説が支持されていた。2010年のDNAの研究によりヨーロッパ人で1〜4%、オーストラリア先住民で6%のDNAをネアンデルタール人から引き継いでいることが分かる。一部が交雑したが3万年ほど前にサピエンスがネアンデルタール人を絶命させている。
10万年ほど前にサピエンスがネアンデルタール人と地中海東岸でぶつかったがサピエンスが勝つことができなかった。その頃のサピエンスの学習、記憶、意思疎通の能力は格段に劣っていた。しかし7万年ほど前いアフリカを離れたサピエンスはヨーロッパや東アジアに達した。4万5千年ほど前には海を渡りオーストラリア大陸にも上陸している。7万年前から三万年前にかけて、人類は船、ランプ、弓矢、温かい服を縫う針を発明した。ほとんどの研究者はこれらはサピエンスの認知能力に起こった革命だと考えている。原因は不明だが、他の動物と違う特別な言語を身につけ、意思疎通の能力を飛躍的に高めた。そして架空のものを語ることができ、伝説、神話、神々が現れた。それらによりサピエンスは150人を超える集団での協力ができるようになり、他の動物を圧倒する。またホモサピエンスの発展は生物学では記述できなくなり、その虚構を記述する”歴史”が必要になる。
歴史という観点では7万年前から1万2千年前までは狩猟採集時代で多夫多妻性だっと考えられるが、石器時代というよりも木器時代であったため、たしかな証拠は少ない。現在に残っている狩猟採集の社会を研究するのは有用だが、農耕が行われなかった土地に住んでいると言った様々な制限がある。とはいえいくつか言えることがある。数百人の集団で住んでおり、一万五千年前から共に暮らす犬を除くと人間だけで家畜はいなかった。インドネシアの島々の海岸に漁村を作った。現地にあわせた生活を送り、周りの自然環境について知識が豊富だった。サピエンスの脳の大きさは狩猟採取時代以降にじつは縮小したという証拠もある。狩りは3日に一回で採集は一日3〜6時間、週35〜45時間しか働かないで理想的な栄養が得られた。子供の死亡率が高いものの80代まで生きるものもいた。多様な食物をとっていたため旱魃の影響も農耕社会よりは大きくなかった。家畜に由来した感染症も少なく小さい集団で移動していたため、蔓延しなかった。しかし事故による死や集団についていけない障害者や老人を置き去りにすることもあった。おそらくアミニズムの信奉者だった。
認知革命後に人類は海を越えてアフロ・ユーラシア大陸の外に出始めた。4万5千年前には海洋社会を発達させたサピエンスが船と航海技術をもって100キロ離れたオーストラリアに到達し住み始めた。3万5千年前に台湾や日本にも到達した。そして人類への恐れを進化させることがなかった200Kgもあるカンガルーやフクロライオン、巨大なディプロトドンなど23種は数千年のうちに絶命つした。同じことは各所で起きた。紀元前1万2千年ごろアラスカからアメリカ大陸への氷河が溶け大挙して移住し、紀元前1万年までにはアメリカの南の果てに到達していた。その過程でマンモスやマストドン、アメリカライオン、オオナマケモノ、ラクダなどが人類の上陸2000年以内に絶滅した。キューバ、マダガスカル、ニューカレドニアも同様。19世紀まで人類が足を踏み入れなかったマダガスカルなどは多様な生物を残した。海の大型海洋生物も同じ危機にさらされている。
ポイント ー 第二部:農業革命
サピエンスは1万年ほど前から農耕を始めた。トルコの南東部とイランの西部とレヴァント地方の丘陵地帯で始まった。紀元前9000年ごろまでに小麦が栽培植物化され、ヤギが家畜化される。他の動植物も家畜化・栽培化が進み紀元前3500年には一通り終わる。現在でも、私達が摂取するカロリーの九割以上は、先祖がこの期間に栽培化した、それらはほんの一握りの植物、すなわち小麦、稲、とうもろこし、ジャガイモ、キビ、大麦に由来する。農耕はいくつかの他の場所でもそれぞれ完全に独立した形で発生したという意見で、学者たちは一致している。農耕民は狩猟採集民よりも苦労して働いたのに、得られる食べ物は劣っており、満足度の低い生活を余儀なくされた。農業革命は、人口爆発と飽食のエリート層を生んだ史上最大の詐欺だった。小麦、稲、ジャガイモなどの一握りの植物種はサピエンスを家畜化した。サピエンスは小麦を守るために、朝から晩まで草取りや水やりをしたり、糞尿で地面を肥やしたりした。サピエンスは農耕への移行によってヘルニア、関節炎などの病気に悩ませれ、個人は栄養不良にも苦しんだが、単位面積あたりの土地からの多くの食料を得ることで千人規模の村がやっていけた。劣悪な環境でも多くのDNAが残せれば進化の勝利だが、誰も合意していない取引だった農業革命は罠だった。また紀元前9500年前に狩猟採集民族の構造物も見つかっている。この神殿の建設に必要な人々を養うために集約的な小麦栽培に移行した可能性もある。
サピエンスは農耕に適する2%の大地に身を寄せていた。農耕民は天候などへの不安から働いた。それらのストレスが政治体制や社会体制の土台だった。農耕民から没収されたエリート層が食べていて、王や兵士、聖職者、芸術家などが歴史を形作っていたが、残りのほとんどの人は田を耕していた。農耕による余剰食料があっても土地や水の対立・紛争、戦争について集団が合意形成できないと不和が生じてしまう。これを回避する大規模な協力ができたのは神話のおかげだ。紀元前3100年にはファラオがナイル川全域を統一し、何十万もの人々を支配した。古代バビロニアのハンムラビ法典もアメリカの独立宣言も神話の例である。キリスト教、民主主義、資本主義などの神話を信じさせる方法はそれを誰かが言っているからではなく神や自然法則が定めたものとする。想像上の世界は物質的な世界や欲望を形作った。個人主義が”個室”を作り、ロマン主義が”旅行”を欲する。また共同主観の世界を壊すにはフランス法制度のような”プジョー”という企業のようにさらに大きな共同主観が必要になる。
共同主観を作っている脳の容量と持続性を補って大量の数理データを扱うために、シュメール人は書記を作った。当時の書記は詩歌などを表せない不完全な書記体系で数字データを記録した。紀元前3000年から2500年にかけて楔形文字に変化し、同様にエジプト人は象形文字を開発し、紀元前1200年頃中国で、紀元前1000-500年頃中央アメリカで別の完全な書記体系が発達した。また膨大な税の記録簿と、それを処理する複雑な官僚制は不完全な書記体系とともに生まれた。9世紀にはインド人が考えた0〜9までの文字で表すアラビア数字が生まれる。
人類の大規模な協力ネットワークを築くためにヒエラルキーや差別を生んだ。白人至上主義やカースト制、貧富の差が生む階層も同じだ。黒人は知能が劣っているからホワイトカラーになれず、黒人はホワイトカラーについていないから知能が劣っているというように、階層が階層を強化した。性別のヒエラルキーはほぼすべての社会で見られ、女性は男性の所有物だとされてきた。2006年でも夫が妻を強姦しても起訴できない国が53カ国あった。紀元前5世紀のアテネでも女性は独立した法的地位を持たず、民衆の議会への参加や裁判官になることなどが制限されていた。また”自然”とされている男女間の関係も主にキリスト教などから来ている。男女の女性の性質も生物学的には何も変わっていないが、男性らしさ女性らしさは社会的には変遷している。社会は男性の優位の家父長制を敷いているが、その優位性に納得のいく答えはない。
ポイント ー 第三部:人類の統一
600年ほど前には人類の9割はアフロ・ユーラシア世界に暮らしていた。残りは4つに分かれていた世界に住んでいた。メソアメリカ世界、アンデス世界、オーストラリア世界、オセアニア世界である。その後300年でアフロ・ユーラシア世界が他の地域を征服した。貿易商人や征服者、預言者は世界を一体化させようと試みてきた。
貨幣は相互信頼の制度であるが、これまで考案されたもので最も普遍的で最も効率的な制度だ。タカラガイは貨幣として使われていたが、シュメールで大麦貨幣が考案され、メソポタミアでは銀の重さが使われた。紀元前640年頃にリュディアの王が初めて価値と発行元の権威が記された硬貨を発行した。膨大な見知らぬ人々が交易や産業などで協力できるようになる一方で、知っている人たちの交流である各地の伝統や親密な関係が損なわれる。人々はコミュニティや神聖でなく、貨幣を信頼する。貨幣が亡くなったら信頼も失われる。そんな無慈悲な社会が訪れるかというというと、そんな単純ではなく、かつては戦士、信者、市民たちが計算高い商人を何度も打ちのめしてきた。
帝国も人類の統一に向かう力になっている。帝国による支配や搾取を批判する声もあるが、過去2500年の間、世界でもっとも一般的な政治組織で、安定した統治形態だった。帝国はエリートを通して芸術分野の発展にも寄与しているが、共通言語も提供している。サピエンスは進化の過程で民族的排他性を発達させているが、支配者は帝国に住む人達の利益のために支配をしていた。小さな文化が持つ思想や財、テクノロジーを融合して、共通の文化を作り、支配を簡単にすると共に正当性を獲得した。21世紀に入り国民主義は衰えてきてグローバル帝国が生み出せれつつあり、多民族のエリートによって支配されている帝国に参加する人が増えてきている。
通貨と帝国と並んで人類の統一を推し進めたのは、宗教だった。宗教とは超人間的な秩序の信奉に基づく、人間の規範と価値観の制度と定義できる。アミニズムは特定の場所や気候、現象の独特の特徴を強調する局所的だったので、王国や交易ネットワークの発達とともにより広範な権威として多神教が生まれた。多神教は一神教を生んだがどれも泡沫的なものだった。ユダヤ教は宣教も行わずユダヤとイスラエルの国民のための局地的な一神教だったが、その中の一宗派がイエスをメシアとして全人類に向けた広範な宣教を始めて成功した。イスラム教も小さな宗教だったが、キリスト教と同じように積極的に布教し勢力範囲を拡大していった。多神教の中でアミニズムが生き延びたように、一神教の中でも多神教の神々が生き延びていった。多神教は善と悪の2つの神を持つ二元論も生み、マニ教やゾロアスター教のように一時勢力を拡大したものの縮小したが、一神教に大きな影響を与えた。個々までの宗教は神や超自然的な存在への信仰に焦点を絞っていたが、仏教は人が苦しみから逃れるすべを普遍的な自然法則として、一時勢力を拡大した。ただ内部に多神教的な神々への崇拝は残った。近代では自由主義、共産主義、資本主義、国民主義、ナチズムなどの自然法則の宗教が多数台頭した。そのいくつかはホモ・サピエンスを崇拝する人間至上主義に分類でき、自由主義的な人間至上主義、社会主義的な人間至上主義、進化論的な人間至上主義の諸派に分化している。
歴史は二次のカオス系であり予想が結果に反映される。たとえば石油市場も二次のカオス系である。明日の石油価格を予測できるプログラムを開発したら石油価格は予想に反して今日変わり、明日の石油価格は分からない。また歴史は人類の良い方に変わってきているという証拠もない。ローマ帝国がキリスト教でなくマニ教を国教としていた方が人類にとって良かったかもしれないが、分からない。ミームという思想のようにキリスト教が有益だったからでなくキリスト教の増殖力が他より強かったから発展していったことも考えられる。
ポイント ー 第四部:科学革命
過去500年にわたって人は科学研究に投資することで自らの能力を高められると繰り返し証明してきた。宗教は重要なことはすべて明らかになっていて異議を認めないものだが、科学は積極的に無知を認め、知識を得る過程で過去の誤りには異議を挟む余地がある。観察結果を収集し、数学的なツールでそれらを説にまとめ、さらにそれらの説を使い、新しいテクノロジーの開発を目指す。統計学を使いスコットランドの長老派教会の牧師はなくなった牧師の妻や子供に年金を支給する生命保険基金を設立することができた。科学は人類に新しい力を与えてくれるが、真の価値は有用性だ。それにはテクノロジーのツールが重要だ。科学とテクノロジーが結びついたのは19世紀にはいってからで主に戦争を攻守から支えてきた。それまでは軍事技術によって救われるとも金持ちになるとも思われたいなかったからだ。科学と産業と軍事のテクノロジーが結びついたのは資本主義と産業革命が到来してからだった。科学革命以前は知るべきことをすべて知っていたムハンマドやイエス、ブッダ、孔子さえもが危機や疫病、貧困、戦争はこの世から無くせなかった。しかし新しい知識を応用することでどんな問題も克服できると、多くの人が革新を持ち始めた。死の問題ですら解決できるとプロジェクトが進行している。しかし科学研究には多額な投資が必要である。それを決めているのはイデオロギーや政治、経済の力を考える必要がある。重要な力が2つある帝国主義と資本主義である。
18世紀半ばにクックがタヒチ島に太陽と地球の距離を測るために派遣されたが、多くの学者を連れていき、ニュージーランドやオーストラリアも寄ったが、その後の100年でヨーロッパ人に侵略されて先住民族が被害を受けた。タスマニアは1万年近く孤立して生きていた先住民族が絶滅した。なぜヨーロッパ人がオーストラリアを始めて探検したのか?その理由は近代前期に2つの潜在能力を伸ばしたからで、それは近代科学と近代資本主義だ。精神構造として近代科学と帝国は自分の無知を認めることで共通していて、以前の帝国は自らの世界観を広めたり富と権力を求めて征服をしたのに対して、ヨーロッパ人は領土に加えて新しい知識を求めるために海を越えて征服をしていった。古代アテネ、カルタゴ、インドネシアを支配していたマジャパピトも未知の海へ出ていくことはなかった。明朝では鄭和が300隻もの船で海を探検したが植民地を築こうとはせずに中国の文化として遠征していたわけではなかったので、この事業が次の支配者には引き継がれなかった。特異なヨーロッパ人だけが「これらの土地はすべて我々のものだ」と宣言したかったのだ。スペインはメキシコを征服した後に10年後にはインカ帝国を征服していた。近代のヨーロッパ人にとって帝国建設は科学的な事業であり、科学の学問領域の確立は帝国の事業だった。紀元前3000年に栄えていたモヘンジョダロの遺跡もその後の周辺の支配者は目に止めなかったが20世紀に入りイギリスの調査隊によってインド人も知らなかった大文明を発見した。楔形文字も1618年に発見されたものの200年以上だれにも解読できなかったが、ペルシアに派遣されたイギリスの士官であったヘンリー・ロンリンソンがザクロス山脈の碑文を見にし写しを作るところから始まり自ら業務の合間に時間を見つけて研究して解読にこぎついた。インドに派遣されたウィリアム・ジョーンズも体系的に言語を比較してインド・ヨーロッパ語族を突き止めた。それぞれの支配地域の知識を深めて効率的な帝国の支配につなげていった。一方でアーリア人は他人種よりも秀でているというイデオロギーも作ったりした。また科学と帝国の隆盛には資本主義という重要な力も潜んでいる。
今の経済は将来のお金で現在を築くという信用で成り立っている。銀行は成長を見込んで預けられる貨幣の何倍も額の貨幣を信用により貸し付けられる。信用そのものは昔からあったが人々は信用供与を行わなかった。当時は経済のパイは限られていて取り合いだったので、キリスト教でも大金を稼ぐことが罪悪とみなされていた。その後、科学革命は進歩という考え方を登場させた。アダム・スミスは利己主義は利他につながると説いた。この資本主義という宗教は、近代科学の発展にも影響を与えてきた。利益を生むプロジェクトのみスポンサーが見つかるからだ。資本主義はヨーロッパ帝国主義にも影響している。コロンブスはスポンサーを探すのに国王を回ったが、のちに株式会社がスポンサーになった。オランダ商人が出資した東インド会社は商業的利益を最大化するためにインドネシアを支配した。インドを征服したのは国家ではなく株式会社であった。政治は何もするなという自由市場資本主義はカルト的である。自由市場資本主義は、利益が公正な方法で得られることも、公正な方法で分配されることも保証できないので、利益追求のため奴隷貿易なども生み出す。資本主義の欠点についてはもう少しで改善されるという意見もあるが、経済のパイの広がりは原材料とエネルギーを使い果たすという警告もあるが本当だろうか?
技術の発達によって、人類が使用できる原材料やエネルギーは過去に比べて実は増加している。それまでは人や家畜の筋肉で行っていたエネルギー変換を、産業革命は熱エネルギーを力に変換するというエネルギー変換の革命だった。それ以降は安価で豊富なエネルギーと安価な豊富な原材料の新しい組み合わせが実現された。工業生産方式が生まれたが動物たちも機械と扱われ工業生産されるようになる。またそれを支えるために消費主義が宣伝された。資本主義と消費主義の価値体系は2つの規律が合わさっている。富める者には「投資せよ」それ以外の者には「買え」である。過去の宗教は楽園を約束されたが、思いやりと寛容さを養い、渇望と怒りを克服し、利己心を抑え込んだ場合のみだった。それに対して資本主義・消費主義の宗教は富める者に強欲でありつづけ、一般大衆が己の感情に従い買い続けることを求めるが、信者は忠実にそれを実際に実行しているので、史上最初の宗教である。信者たちは楽園が手に入ることをどのようにしるのか?それはテレビを通じてである。
サピエンスは発展の過程で多くの種を絶命させてきたが、それは汚染や自然災害を引き起こし自分たちの種に住みにくい環境になる可能性もある。これを多くの人は”自然破壊”と呼ぶが、実際には”変更”である。自然は決して破壊できない。小惑星による恐竜の絶滅は哺乳類繁栄への道を切り開いた。6500年経つと知能を得たネズミたちは人間が起こした現在の大量殺戮に感謝するかもしれない。サピエンスは自然の気まぐれに振り回されなくなった一方で、産業の命令に支配されている。伝統的な農業のリズムは時間という新たな活動のテンプレートに置き換わった。その他では都市化、工業プロレタリアートの出現、庶民の地位向上、民主化、若者文化、家父長制の崩壊など大激変をもたらしたが、最も大きい社会変革は家族とコミュニティという人間社会の基本構成要素をバラバラに分解し、国家と市場の手に移したことだ。かつての王国や帝国はみかじめ料を取り立てる見返りに、近隣の犯罪組織や地元のチンピラなどが、自分の庇護下にある者たちにけっして手を出さないようにしていただけで、他は何もしていないに等しかった。それ以外のことは家族やコミュニティにまかせていたが、それは緊張関係と暴力に満ちたものだった。産業革命は市場と国家に力を与え、政府が自由に人々活用できるようにしたが、家族やコミュニティによって、国民主義的な教育制度の洗脳や軍隊への徴収、都市のプロレタリアートになっているのを阻まれた。国家や市場は、警察や裁判所を家族の監視や判決の代わりに導入し、さらに「個人になるのだ」と提唱し、家族やコミュニティを打ち砕いた。国家と市場は個人とは対立しておらず個人の生みの親である。以前は親の権威は神聖視されていて、親を敬い、従うことは尊ばれる価値観であったが、今日ではその権威は見る影もない。部族の絆を感情面の代替え物として、消費主義と国民主義は想像上のコミュニティを育成させてきた。マドンナのファンであるなど同じものを好きである消費者部族や国民神話などである。この二世紀の変革は大きいが、特に世界大戦後の70年以上の平和は格段に大きな変化である。以前はコミュニティ同士の復讐やコミュニティ内の犯罪で多くの命を奪っていたが、それが減り戦争や犯罪など暴力による人々に死亡は自殺により死亡よりも少ない。またヨーロッパの諸帝国の崩壊もこの平和に寄与している。国家間の戦争も減っている。理由としては戦争の代償が大きい一方で戦争の利益が減ってきた。
過去500年間の革命は人類を幸福にしたか?中世時代より幸福だし、石器時代の狩猟採集民よりも幸せに違いないという進歩主義的な見方は説得力にかける。また人間の能力と幸福度は反比例すると主張するロマン主義的な見方も小児死亡率の現象や、戦争や飢饉の激減を考えると独善的だ。この最近の黄金期も後で振り返ると人類繁栄の基盤をそこなう原因の種を巻いている可能性もある。幸福度の測定にはヨーロッパ人だけ、男性だけではなく、犠牲になっている動植物を感情に入れずに人類だけというのも誤りだろう。研究結果では、富はある程度まで幸福に影響する。悪化しない病気は短期的に幸福度を下げるのみである。家族やコミュニティは富や健康よりも幸福感に大きく影響を与え、結婚生活が良好か劣悪かは大きな影響があることが研究により繰り返し示されている。過去二世紀で物質的な改善は、家族やコミュニティの絆の悪化により相殺されている可能性はある。一番重要な発見は幸福は客観的な条件と主観的な期待の関係によって決まる。牛に引かせる荷車がほしくて、それが手に入ったら幸福だが、フェラーリがほしくて、フィアットの中古車しか手に入らなければ惨めと感じる。現代のティーンエージャーは広告に出てくる映画スターや運動選手、スーパーモデルと自分と比べて自分に満足できない。化学から幸福を見ると、それはセロトニンなどの分泌だ。その分泌は永続的には続かないようにできており、現代の銀行がペントハウスを買った時と、中世フランスの農民が泥壁の小屋を立てた時で、セロトニンの分泌が変わらなかったら彼らの幸福度は変わらない。死後の幸福を信じる中世の人々の方が信仰を持たず目的のない人生を歩む現代人より幸福かもしれない。幸福は人生の意義について自分の妄想を集団的妄想に一致させればよいのか?仏教は幸福の問題を重要視してきたが、ブッダが教え諭したのは、外部の成果の追求だけではなく、内なる感情の追求もやめることだった。たいていの人は自分の感情や思考、好き嫌いと自分自身を混同している。感情は自分自身とは別のもので、特定の感情を執拗に追い求めても、不幸に囚われるだけであることに、彼らは決して気づかない。
ホモ・サピエンスは自然選択の限界を突破するかもしれない。知的選択というものはなかったが1万年前に農業革命の間に変化が訪れた。選抜育種によって特異な選択圧をかけた。現代では科学者たちは遺伝子工学によって生き物を操作している。一つは生物工学によって大腸菌や菌類も改変されており、哺乳類も実験がされている。ジュラシック・パークのようにネアンデルタール人やマンモスを復活させることもできるが、人類を設計すればホモ・サピエンスはホモ・サピエンスでなくなる。また一部を機械化してバイオニック生命体を作ることもでき、脳をインターネットにつなぐこともできるが、意識や記憶やアイデンティティにどんな影響があるか分からない。このようなサイボーグのもつ心理的・哲学的・政治的な意味合いも分からない。あとは完全な非有機の自己増殖するもの、たとえばコンピュータ・プログラムも生まれるかもしれない。そしてある時点で過去の意味がなくなるビッグバンような特異点が到来する可能性がある。科学の進歩を止めることはできないが、影響を与えることはできるかもしれない。私達は何になりたいかではなく、何を望むかを考える時である。
サピエンスは飢饉や疫病、戦争を減らし、人間の境遇に関しては多少は進歩した。とはいえ他の動物達の境遇はかつてない速さで悪化している。人間の力は強力だがその力をどこに使ってよいかは、ほとんど見当もつかない。物理法則しか連れ合いがなく、神にのし上がった私達が責任をとらなければならない相手はいない。他の動物達を悲惨な目に合わせているが、決して満足しない。自分が何を望んでいるかもわからない、不満で無責任な神ほど危険なものはるだろうか。
最後に
ポイントを掻い摘んで説明したが、多くの要素があり要約のようになった。気になるのは「ビッグバン」で話が始まっているが、典型的な科学が強化している現代の物語だと思う。全体的に整理された抽象的な議論の中に、具体的な歴史的な逸話が折り挟まれていて、著者の広範な知識と広大な物語を整理する論理力に脱帽する。サピエンスの歴史が綺麗に整理されているので、理解はしやすいし、発展的にまたは批判的に著者の説を見ることができて素晴らしい。
サピエンスのDNAも実は少しは混ざりながら発展してきているというのと、宗教というミームも土着の信仰と混ざりながら広がっているというのが気になった。1->2->3というのではなくて、1,2,2.5,3などが同時的に存在している。あと貝が通貨というなら貝塚は銀行だったのな。科学革命で現世を改善できるので現世主義になってきたというのは面白い。日本が例外的に19世紀の末に西洋に追いついたのは社会や政治を西洋を手本として作り直したからだと書かれているが、他の国ができなくて、なぜ日本にそれができたのかは他の書籍で勉強したい。戦争を克服して減ってきていると描いてあったが、戦争が経済的なものであれば、侵略は日本でも日々進んでいると感じる。
とにかく歴史的情報と新しい視点などが多く、いろいろな発見や歴史についても学べる貴重な一冊であるとは思うので、歴史や経済に興味がある人だけでなく、科学やテクノロジーに関わっている人は読むべき本と感じました!