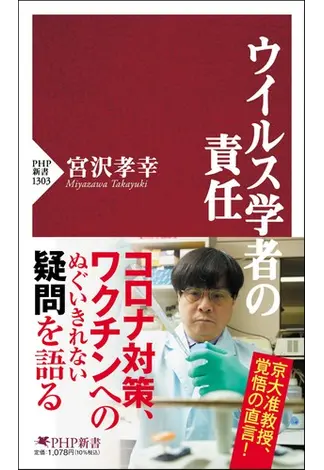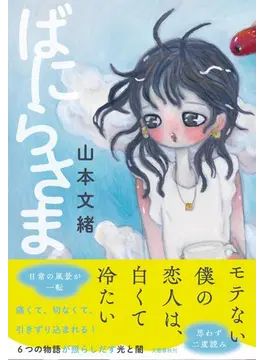復刻版ダイレクト出版 1943 菊池寛
GHQが発禁にしたというのに惹かれて読んで見た。日本男子なら読んだ方が良い一冊。簡素で細かく章立てされていて、読みやすい。
第一章 廃藩置県
大久保利通が転向し公議政治を否定して、薩長連合をもって国内統一を図る。西郷隆盛という旧勢力の重鎮を呼び寄せ、廃藩置県を了承させ断行する。西郷隆盛がどういう存在でどういう役回りだったのかが良くわかった。
第二章 征韓論決裂
西郷は征韓論を唱えるが、決裂して、帰国する。
第三章 マリア・ルーズ号事件
支那の人をアメリカに売る奴隷貿易をしていた船が難破する。あえて公法をたてに日本で裁判にかけ清国に奴隷を引き渡した。
第四章 西南戦争
西郷は鹿児島に帰ったが、鹿児島で西郷王国を築くが如くである。内務改革のために鹿児島県の役人を更迭する人事が行われる。さらに西郷を暗殺する計画があるときき、軍を組織する。二百日も転戦するがついに西郷の自害とともに幕を閉じる。
第五章 十四年の政変
内務卿の大久保も刺客に殺される。その後釜とし伊藤博文か大隈重信ということになるが、大隈重信はその職を免ぜられるというクーデターがあった。これは北海道開拓使有物払い下げ問題に端を発して、薩長政府に批判が集中した。これを伊藤が利用して逆に土佐の政敵を葬ったとしている。
第六章 自由党と改進党
板垣退助も武人で、西洋との人民の在り方の違いを憂いていた。なぜ人民が国や地域のために戦わないのか?ということだ。また土佐の坂本龍馬以来の民権思想も引き継がれて、板垣退助は自由党を作る。またより穏健な政党として肥前出身の大隈重信が立憲改進党を作った。土佐と肥前が政府の薩摩と長州に対抗したとも見える。
第七章 国軍の建設
大村益次郎は軍政家として国軍の改革を進めていたが、保守主義者の刃にかかって死ぬ。その後を継いだのが洋行した山縣有朋であり、徴兵制をしく。土百姓や素商人に鉄砲をもたせて何ができるかという雰囲気だった。山縣は平民から組織された奇兵隊の力を見ていた。また大村は内乱鎮圧を目的としていたが、山縣は外敵を目的としていた。桂太郎はドイツで軍を研究していたが徴兵令を評価した。またメッケルを召喚し戦術を抗議した。
第八章 憲法の発布
伊藤は憲法の視察のために洋行するが、デモクラチック・エレメントが必要で、それは今までの日本にないものとしている。神武天皇以来の大きな変遷としている。日本に帰ると横須賀の夏島につめて秘密裏に井上、伊藤、金子とともに草案を書く。特に皇室典範を担当した井上毅の仕事が大きいとしている。明治天皇も一条一条を確認した。
11月12日の会議中に四男が亡くなった知らせを受けた明治天皇が会議を続けなさったとのことに驚いた。他国では憲法の発布とともに流血があるというが日本がないというのは、いろいろ考える。
第九章 大隈と条約改正
大隈は鹿鳴館の猿芝居がこたえて、不平等条約改正のために再び政府に入って動き始める。自分が東京で交渉する形をとった。メキシコで成功すると、米国、ドイツと条約を改定していった。英国と交渉する段になり、秘密裏に進めていた条約の概要が英国の新聞に載ってしまう。条文に憲法違反になる項目があることがわかり、世論が沸騰し、ついに爆弾の被害に遭って、条約改正は頓挫してしまう。
第十章 日清戦争前記
朝鮮の扱いをめぐって支那と対立する。伊藤博文は李鴻章と会談を持ち天津条約を調印する。朝鮮に東学党が政治革命を企てるのに乗じて、支那は朝鮮に出兵する。
第十一章 陸奥外国の功罪
陸奥宗光のこれまでについて。伊藤は軍部と協調して、講和の交渉相手を残しつつ戦いをした。清国側から講和の申し出あり米国を仲介として下関に李鴻章一行を招き行われた。交渉三日目に李鴻章が狙撃される。伊藤はなぜ俺を狙撃しなかったのだと言ったという。一転、日本は不利な状況に転じたが、挽回して、下関条約を結んだ。
伊藤博文が中国語を少し話せるのは驚いた。
第十二章 三国干渉
国民が戦勝に酔いしれている中、ロシアは遼東半島の放棄を求めてきた。その後、ドイツ、フランスも同一の覚書を持ってくる。イギリスも当初は同様な論調だったが、ロシアの拡大を懸念し、むしろ日本側につく。イギリスはインドでもロシアの脅威にさらされていた。結局、遼東半島を放棄する。著者はなぜ未来にわたっても遼東半島を他国が割譲しないことを約束させなかったのか?と悔しがる。
第十三章 川上操六と師団増設
三国干渉があり、軍拡が世論となった。川上操六は一人で日清戦争の陸軍を指導したと言われている。モルトケに指導された川上の話が続く。国防の観点から内地は元より、朝鮮や支那へも旅行している。川上は河野広中に六ヶ師団増設をロシアが想定するよりも早く準備することで優位に立てるとして認めさせた。
権力に興味がなく、死ぬ頃には人当たりは益々柔らかくなり、給仕の少年にまで一々挨拶を返した、という人柄は心を打った。
第十四章 北清事変
列強たちは清国の利権を取得していった。ロシアは鉄道、旅順、大連。フランスは南全体、海南島。イギリスは威海衛や九龍半島、鉄道。民衆は政府は当てにできなかった。そんな中、山東省に起こった義和団は外国人駆逐に熱を上げて、支那全体に広まった。ついに天津居住地を攻撃し、北京の各国の公使館を包囲するに至った。各国は兵を持っていたが挙匪と官兵も加わっていて膠着状態になる。英国も日本も当てにしだす中で、天津で露独仏の連合軍が負けた翌日、日本が占拠した。日本を加えた混成軍が北京に向かい各国兵が功を急いぐ中、正面から撃破して、包囲された人々を救った。占領された清朝末期の北京は天下の宝物に溢れていたが、日本兵は保存のために尽力した。一方の列強の各国軍は略奪や破壊、婦女への暴行を尽くし、日本に助けを求めるほどであった。
第十五章 対露強硬論と七博士
韓国大使に任命された林権助は陸軍の参謀将校から対ロシアの観点で朝鮮の防衛が大事だと言われる。一年後、ロシアの艦隊が来ると基地を作ろうとしている場所を聞き込んで、その土地を商社に買い占めさせた。このような積極的な対露路線に対して、伊藤博文は消極的な態度をとっていた。満州でロシアの権益を認める代わりに韓国で日本の権益を見てめてもらうという満韓交換論である。軍も議会もロシアと開戦する時期を逸すと紛糾し、民間の学者も開戦を進言した。
当時は軍も政府もかなり風通しの良い組織だったことに驚かされた。
第十六章 日露海戦
日本は日英同盟や満州還付条約など日露海戦への外交上の布石を打っていた。内政としても桂内閣と伊藤博文が和解をして外交の一本化を図った。桂首相も明治天皇へも報告を入れている。その折、露国参謀本部では対日作戦計画の裁可がおりて、増援部隊が到着し次第、日本に戦争を始めるという情報が届いた。日本は御前会議を開き満場一致で開戦を決議し、翌日に軍は勅諭を賜った。財政面も不安があるなかで、伊藤博文は金子伯をアメリカに派遣して、調停への布石を打っておくように頼んだ。その時の言が以下である。
「いよいよロシア軍が海陸からわが国に迫った時には、伊藤は身を卒伍に落して鉄砲をかつぎ、山陰道か九州海岸に於て、博文の生命のあらん限り戦い、敵兵に一歩たりとも日本の土地はふませぬ決心である。昔、元寇の時、北条時政は、身を卒伍に落として敵と戦う意気を示した。その時彼は妻に何と言ったか、汝も吾と共に九州に来れ。そうして粥を炊いて兵士を労えと言った。今日伊藤も、もしそんな場合になればわが妻に命じ、時宗の妻と同様に九州に行って粥を炊いて兵士を労い、そうして斯く言う博文はは、鉄砲を担いでロシアの兵と戦う。」
金子は伊藤の熱意に動かされて、アメリカ行きを承諾したが、参謀本部に児玉次長を訪ねて戦局観を聞いた。「まあ君がニューヨークで演説している最中、六度は勝報がいくだろうが、四度は負け戦の電報が行くものとして覚悟していてくれ」と答えた。海軍の状況を山本に聞きに行くと、「僕の方は半分は軍艦を沈める。又人間も、半分は死んでもらわねばならぬが、君もアメリカでどうかその心算でやってくれ」と言われる。
第十七章 児玉総参謀長
参謀次長がなくなり、降格になるが児玉がその地位に治った。前任の田村の作戦をさらに練りあって作戦を決定した。メッケルも児玉を英才としていた。台湾総督にも選ばれ混乱した台湾を建て直した。どの地位にあっても人ができない成果をあげている。
第一軍は仁川から順次上陸させ、一気に北上し鴨緑江岸九連城付近で敵の軍とはじめて遭遇し、これを撃滅させ、全軍の士気を鼓舞した。第二軍は遼東半島の敵を駆逐するため、半島の一角へと敵前上陸を敢行し、旅順港内の敵戦を撃沈したりした。一軍が大勝したその時に第三軍の大将として乃木に声がかかる。乃木は児玉とは西南戦争からの知り合いで、反対の性格だったがウマがあった。第四軍まで編成されたが軍事司令官は維新からの歴戦者たちで、補佐する参謀長は士官学校の一期生二期生ばかりだった。満州総司令部が設置され、悠然と構える大山を尊敬していた児玉は人を食ったような態度はなく慇懃に務めた。
第三軍は旅順を攻めた。第一回攻撃でも第二回攻撃でも大量の死傷者を出しながら戦況はまったく好転しなかった。歯がたたない旅順の要塞のために、二十八柵の巨砲を内地から運んだ。据えるのにも一二ヶ月かかるような大砲を横田大尉の超人的な努力でわずか九日で発射の準備ができた。しかし思ったような戦果はあげられなかった。ここでやっと正面攻撃を反省をして203高地という比較的手薄な場所を目標にする話も出てきたが、変更はまとまらず正面攻撃は続いた。203高地に目標が移されると、9昼夜連続の攻撃で屍山血河という言葉通りの戦場になる。児玉も戦況が良い時は冗談を飛ばすこともあったが塹壕内を往復し203高地の下を匐伏して戦況を視察した。203高地から旅順の街が見えると、二十八柵砲を中枢部や敵艦に向かって飛び、敵艦はほぼ殲滅した。これにより他の地域も占領し、開城を迫った。旅順に入場した第三軍は陣没将士の鎮魂祭をした。終わるとただちに奉天に向かう司令を受ける。
第十八章 奉天会戦
両軍の戦闘品は日本軍が24万、露軍が36万。当時世界でも例のない規模だった。日本は劣勢だったがとった作戦は包囲作戦だった。孫子に「十ならば即ち囲む」とあるが、十倍の戦力で初めて包囲は成功するのだ。ロシアでさえこの事実をなかなか認めなかった。しかし日本軍少数での包囲は危機的でところどころに綻びがあった。日本の右翼を餌にして左翼の第三軍を急進させて回り込ませるという作戦だった。ロシアは旅順を堕とした第三軍を心配していたが、右翼にいた第三軍11師団にロシアが気付き、予備兵をすべてこれに当ててしまった。正面左側の第二軍が半数を失う中、第三軍は急進行した。そんな中、敵の左翼は敗走し始め、第三軍の近くの鉄道から退却する列車が見えていた。戦闘はまだ奉天市内や郊外で行われていたが、日本軍は堂々と奉天入場式を行い、南門から入城した。東洋の地で、はじめて完全に武装された東洋人が、白色人種を完膚なきまでに叩きのめした。
第十九章 日本海海戦
くロシアの海軍は開戦時は戦艦七隻、装甲巡洋艦十隻であったが、開戦と同時に仁川港で二隻、旅順港の夜襲で三隻を失っている。陸上の敗走により士気が上がらないためにバルチック海にある精鋭艦隊を日本海に派遣することを決める。周到な準備を終えたロシア軍艦はクロンスタット港を出発し、紅海とアフリカを回る二手に分かれ、落ち合ったのち、日本に迎い、いよいよ津島海峡東水道を通過した。警戒をしていた日本はそれを発見する。日本戦隊の無線が激しくなったことでロシアが発見されたことを知る。
日本も「敵艦見ゆとの警報に接し、吾戦隊は直ちに出動、之を殲滅せんとす。この日、天気晴朗なれど波高し」という有名な第一方が、まず大本営に飛んだ。敵艦隊と並進しながら報告し、その報告は、敵の戦列部隊が太平洋第一、第二艦全部に特務艦が七隻あること、その陣形が二列縦陣であること、その速力は十二浬であることなど詳細を極めた。そこで東郷提督は時刻と距離を計算して、午後2時ごろ、沖の島北方で主力艦隊が敵を迎える予定を立てた。敵艦は予定のごとく姿を現した。「皇国の興廃この一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」このまま進めば、両戦隊は縦陣を以てすれ違い、互いに敵を左舷に見る反航戦になる。利害共に等しいから、先頭としても平凡に終わりそうである。
日本海海戦に於ける丁字戦法は有名だが、黄海海戦でも行ったことがあり日本海軍戦法の定石だった。ただこの日に、この戦法をやるには、あまりにも彼我の距離が近すぎた。それは朝来ガスが海上一面を蔽っていたため、遠望がきかず、敵影を認めるのが遅かったため、強いて旋回をすれば敵弾を浴びなければならず、むしろ避けなければならないのである。東郷大将は突然右手を真直に挙げ、左へ振ると、参謀長を見た。わが戦隊が敵八千メートルに於て、逐次旋回を試みるや、敵の旗艦にあったロジェストウェンスキーの幕僚たちは手を拍って「我勝てり、東郷狂せり」と叫んだという。先頭の三笠は敵の巨砲の前に暴露し、甲板に数弾を浴びた。しかし逐次旋回したわが第一第二両艦隊十二隻の精鋭は、敵の二列縦陣の戦闘を遮り、丁字先方が出来上がった。ここで形勢は逆転し、敵の二列の戦闘艦たるスウォーロフとオスラビーヤはわが片舷百二十七門の巨砲の前に、すっかりその全体を暴露することになった。この二艦を目指して打ち出した砲撃に二艦は煙に包まれて見えなくなった。日本艦隊はロシア艦隊に比べて速力は五割ほど優れていた。この快速を利用して急旋回をした日本艦隊は更に乙字型をなして、あくまで敵の先頭を圧迫するので逃げられない。スウォーロフは全艦蜂の巣のようになり列外に出て、オスラビーヤは炎上後に沈没した。開戦三十分にして、すでに勝利に対する確信を掴んだ。夜も魚雷攻撃で1艦は沈み、3艦は航海不能になる。翌日も五艦はそうそうに白旗をあげた。
第二十章 ポーツマス会議
ニューハンプシャー州のポーツマスが軍港が整備されているという理由で講和の地として選ばれた。小村寿太郎が全権大使として選ばれれ、出発は国民の期待があり盛大なものだった。しかし政府関係者は困難な仕事として考えており、伊藤博文は帰還の際は自分は出迎えると伝えている。交渉相手は海千山千の王男ウイッテだった。小村は遅れて到着するが当てられたホテルの一室を二時間で事務所に改造した。初日の本会議で我が方の十二条よりなる講和条件を提示した。ロシアのまだ負けたわけでないという態度によって難航したが、講和は成立した。賠償金は放棄し、樺太の半分を獲得した。
講和を成立させて日本に戻っていた小村に耐えられないニュースが舞い込んだ。米国の鉄道王ハリマンとの南満州鉄道を共同計画しようというハリマン協定である。小村は諸元老たちを説得してまわりついに協定の取り消しに持っていく。
第二十一章 明治の終焉
日露戦争で勝利した日本は東亜で指導的地位をかくりつした。韓国での日本の宗主権が認められると、伊藤博文は総督として京城に赴き近代化を図った。伊藤は後藤新平で厳島で会談した。大アジア主義を唱える後藤を諌めたが、各国を回ることは了承し、人と会うためにハルビン駅に着いたが、そこで凶弾に倒れた。
明治を通して日本は外国が二三百年かかってなした変革をわずか50年で成し遂げた。外国文化の接種においても常に日本の伝統が基調をなしていた。