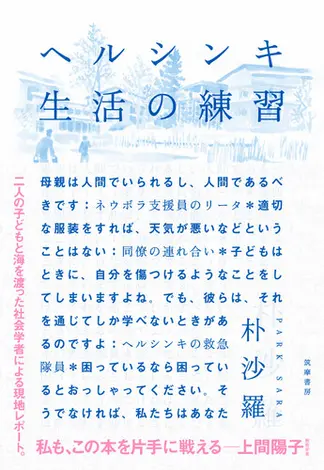
「日本との最大の違いは、保育園に入る権利は、保護者である親の労働状況にではなく、子供の教育を受ける権利に紐付いていることである」
フィンランドの保育園のことが書いてあると読んで手にとった。日本の保育園の利用者としては気になるところだ。二児の母であり社会学を専門とする筆者のフィンランドへの移住体験を中心としたエッセイ。
本の構成
著者は父親が在日韓国人で母親が日本人の”ハーフ在日”である。6歳と2歳の子を持つ母親でもある。話はヘルシンキの職場に採用され、フィンランドへの移住を決意するところから始まる。ヘルシンキに降り立つと、家探し、銀行口座解説、保育園探し、と外国での生活に必要なことを行う。その中で保育園や就学前教育の制度なども説明される。外国人IDはカードのプラスチック(ラミネートフィルム?)がないということで2周間のところが4週間待たされたりして、最悪だというような感想も漏らす。決してフィンランドが日本よりも素晴らしいというような論調ではない。
中盤は保育園の内容や、子育てなどで精神的に追い詰められて外国人向けの相談所に電話した話。後半は自分の過去の生い立ちなどを中心に語られる。
口座が作れての保育園のことを越えて日本や自分の生い立ちについても書かれている。
筆者は在日社会にもなじめず日本社会でもマイノリティーとして暮らしていて、もともと生まれなどを気にしなくても良い外国への憧れもあったことが語られている。日本で在日+女性+母親というのはハッキリ言って三重苦だ。日本社会は在日を嫌い排除し、女性を嫌い排除し、母親を嫌い排除し、おそらく(舌打ちされたり)子どもも嫌っている。筆者が外国を目指すのは理解できる。もしかしてユダヤ人も同じようにして世界中に散らばっているのかもとも思う。一方で社会学が専門なので細かい社会制度などが客観的に語られて、日本と比較されている。
気になったポイント ー 日本社会の息苦しさ
「私は日本にいるとき、ずっと息苦しいような、とてもひどい社会に生きているような気がしていた。その感覚はうそではない。実際に、2020年の3月から4月にかけて、日本に住んでいた知人の心理的な負担感や閉塞感は、紛れもなく本当で、それは自殺者の数となって現れている。」
2020年5月のオンライン調査によると、日本の指導者の評価は世界で最低、逆にフィンランド政府は概ね評価されていた。一方で人口あたりの死者は日本のほうが少なく、補償の規模も日本の方が多い。筆者は日本人たちが苦しいと感じている理由は政府・政治と別なところに起因しているのではない?と疑問を呈している。
私も息苦しいと感じているのを見ることがあるので、これは重要な点だと感じた。個人的には多くの人が暗黙的に作り出す”世間”の狭量なスタンダード(標準化されたルール)などが生きにくくしている気もする。そのスタンダードの一つが”おもてなし”だ。タクシーやコンビニでも海外のサービスに慣れると日本の”おもてなし”的な対応は異様さすら感じる。一昔前は少しぶっきらぼうでも良かったのではないか。社会が個人に求めるハードルが変に上がってしまい、適応障害者を生み出しているのだとしたら、”おもてなし”は消えてなくなってほしい。
気になったポイント ー 共助と公助
「京都で通っている保育園は、(中略)保護者の共同体でもある。(中略) 保育園だけを比較するなら、おそらく京都の保育園のほうが、子供と親を育てる共同体としてのスキルの蓄積と保護者・保育士・経営者の団結力と友情において、この、ヘルシンキの畑の学ん赤にある保育園絵より優れているように感じる。
でも、そんな共同体も、保育園の先生たちの情熱や努力も、保護者の熱意や協力も、もしかすると必要ないのかもしれない。保護者の労働時間が短く、保育が労働者の福利厚生でなく子ども個々人の権利として制度化されているならば。そして皆がある種の『あたたかさ』を求めないのであれば。」
フィンランドの保育園は朝の八時から八時半までの間に登園すると、給食の朝ごはんが食べられる!行事もほぼなく、保護者どうしの交流もない。日本の弁当文化を「すごいねー」と言われる一方で「それはいつ必要なの?」と聞かれる。公助を充実させる運動をせずに、自助や共助で何とかしようとしてしまう日本。それが今の不幸な日本を演出している一要素だとも私には読めた。
気になったポイント ー スキル
「『正直さ』『忍耐力』『勇気』『感謝』『謙虚さ』『共感』『自己規律』などなどを『才能』でなく『スキル』ととることについて、なんとなく狐につままれたような気分だった。(中略)
私は、思いやりや根気や好奇心や感受性といったものは、性格や性質だと思ってきた。けれどもそれらは、どうも子どもたちの通う保育園では、練習するべき、あるいは練習することが可能な技術だと考えられている。」
保育園の面談で子どもが練習が足りているスキルはどれかとスキルが書いてあるカードを並べだした。日本では性格や性質と理解されているものが”スキル”として理解されていて、保育園の先生たちは「いいところ」「悪いところ」という発想を持っていなくて、「練習が足りていること」「練習が足りていないこと」と捉えている。
この発想は面白い。このような発想で子どももそうだが、親とかマネージャの上司など、暗黙知になっているようなスキルを可視化して練習するようにすれば世の中もっと良くなるのではないか。よくよく考えると私の所属するスーパーホワイト企業はマネージャーに対してかなり頻繁に研修をしている。何度も練習を重ねているのかもしれない。
気になったポイント ー 在日コリアンと平和
「中学生あたりから、何度か『日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか?』と質問されるたびに、くちでは『どっちでしょうねー』と言いつつ、心の中では『私がどうしたらいいかオロオロしている間に、お前みたいなやつが私を殺しに来るだろうから、私がその質問の答えを考える必要はない』と思っていた」
たしかに在日コリアンの人は関東大震災でもデマが流れて殺されたらしいので、有事の際に在日コリアンの虐殺は起こりうる。筆者の両親が子どもよりも自分の人生を優先し、戦争反対の集会やデモにをしたことを作者は苦々しく記憶している。けれど、上の話にあるように有事に命の危険にさらされるのであれば、戦争などを避けようとする運動を積極的に行うのはもっともな気もする。筆者は戦争は辛く苦しいことという戦争反対な立場をとっているが、戦争は誰かの経済的な利益のために行われ、一般国民が犠牲になる。そして残念なことにそのような経済的な利益のために一般国民が犠牲を強いられるのは戦争だけではなくて、現在の日本や世界で現在進行系で見かけることである。
最後に
作者は最後に『たくさん友達を作って、粘り強く、できる範囲で、みんなで力を合わせて社会を変えていこう』と呼びかける。人々が助け合う制度のある社会や”公”がある国があることで、それは人々の力で作っていけるのだと感じた。
フィンランドの諸制度や保育園などを知りたい人だけでなく、保育園・幼稚園を使っている子育て中の親たちには響くないようがあるはずなので、ぜひに読んでもらいたい。
