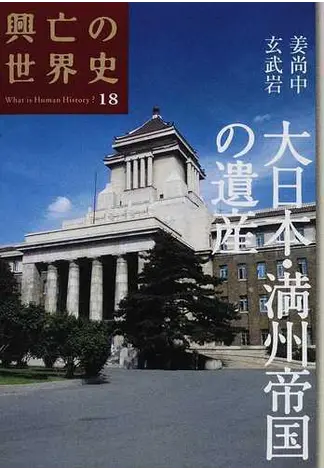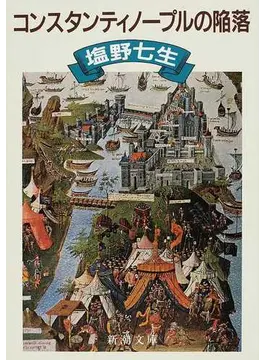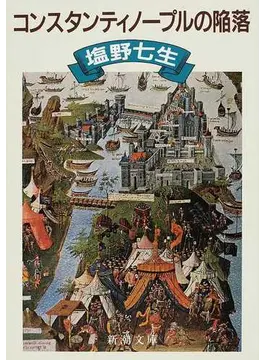 2009 新潮社 塩野 七生
2009 新潮社 塩野 七生
「スルタン・マホメットは二十二歳、均整のとれた身体つきで、身の丈は、並より高い方に属する。武術に長じ、親しみよりは威圧感を与える。ほとんど笑わず、慎重でいながら、いかなる偏見にも捕われていない。一度決めたことは必ず実行し、それをする時は実に大胆に行う。
アレクサンドロス大王と同じ栄光を望み、毎日、ローマ史を、チリアコ・ダンコーナともう一人のイタリア人に読ませて聴く。ヘロドトス、リヴィウス、クルティウス等の歴史書や、法王たちの伝記、皇帝の評伝、フランス王の話、ロンゴバルド王たちの話を好む。トルコ語、アラビア語、ギリシア語、スラブ語を話し、イタリアの地理にくわしい。アエネーアスが住んだ土地から、法王の住む都、皇帝の宮廷がある町、全ヨーロッパの国々などが色分けされ印しを付けられた地図を持っている。
支配することに特別な欲望を感じており、地理と軍事技術に最も強い関心を示す。われわれ西洋人に対する誘導尋問が実に巧みだ。このような手強い相手をキリスト教徒は相手にしなければならないのである」
p.128のヴェネチア共和国特使マルチェッロに随行した副官ラングスキの報告
ローマ帝国から続きビザンツ帝国に引き継がれた首都コンスタンティノープルの陥落。それは1000年のローマ帝国の終わりであり、ローマ文明の終焉をも意味していた。数多くの記録が残っている歴史的な瞬間を両方の陣営から描いた物語仕立ての歴史小説である。
ローマ帝国の終わりにつながる戦闘を22歳の若いスルタンであるメフメト二世が主導していたというのは驚異である。後世に月日まで明確に伝えられているコンスタンティノープルの陥落を知りたいと手にとった一冊である。
本の構成
物語は49歳のビザンツ帝国のコンスタンティヌス11世とトルコ(オスマン帝国)の22歳のスルタン・マホメット、それぞれの生い立ちから始まる。後世に記録を残した6人の人々を紹介し、彼らそれぞれから見たコンスタンティノープルの陥落を描く。そのうち一人はマホメットの美しい小姓トルサンでスルタン側の視点を担う。序盤はビザンツ帝国側が三重の城壁に守られてトルコ側が劣勢になるが、スルタンの奇策も功を奏し、ビザンツ帝国側が押されてくる。
塩野先生の文章は読みやすく、分量も多くはないので、物語はすらすらと読みすすめることができた。一方で物語さを出しているためか地図などが少なく戦闘の全体像などを捉えにくい。ローマ人の物語のような戦場の地図などがあればもっと良かったが、他の資料などを見るしかない。
気になったポイント1ー 大砲という技術革新
この戦闘ではスルタンが巨大な大砲の開発に成功することで、何度も敵を撃退したコンスタンティノープルの三重の城壁に挑もうとしている。さまざまな技術革新はローマでも重要だったが、新しい技術に投資できる国力があったからこそ、この戦闘を有利にできたと読めた。この他にもジェノバ人の船をコントロールする技術や、坑道を掘る技術とそれを探知する技術。
火薬から始まって、コンピュータ、レーダー、GPS、インターネットなど。戦争を有利にするために生まれた技術はいろいろあるが、この時代も戦争によって技術は発達し、技術に投資ができる経済力がある組織が勢力を拡大していたことを確認できた。
気になったポイント2 ー それぞれの弱さ
ジェノバ勢とヴェネチア勢の仲間割れや、なかなか応援に来ないヴェネチア軍など、商人たちはトルコとの通商が先立つのか単純に反トルコでまとまることができず折に触れて反発し合う。一方のトルコも陸上戦は混成部隊だが背後に構える常備軍のイエニチェリに切られるのが怖くて前進するしかない。そうして決死での前進が強さを生み出している。ただ常備軍を持たない海戦では急ごしらえの海軍ではジェノバなどの海の民たちには太刀打ちができず敗戦を経験する。
包囲されるビザンツ帝国も消耗戦だが、包囲しているトルコも10万の兵の食料を調達したり、士気を保つのも簡単ではない。どちらかが優勢というわけではなく、ギリギリの戦いだったというのは印象的だった。
最後に
包囲を50日続けていても、砲撃を絶え間なく続けていても、外壁を越えた人は一人もいなかった。そんなときにカリル・パシャは説得する。「攻略は断念し、包囲は解くべきである。亡きスルタンも経験したことだから、撤退は決して恥ではない。無謀こそ、大国をひきいる者の、してはならないことである。」と。しかしそれでもスルタン・マホメット諦めなかった。そしてコンスタンティノープルを陥落させ、キリスト教世界に衝撃を与えた。
ところで、アレクサンドロス大王に憧れたスルタン・マホメットが憧れた人のように”大王”として扱われているかというと、今のところそうでもない。それは彼の功績というよりも後世への伝え方だったりするのかもしれないとも思うが、学者を連れて遠征をしていたアレクサンドロス大王ほど伝える努力をしていないからなのかもしれないし、世界がもっと複雑になっていたからかもしれないし、積極的なスルタンと消極的な官僚機構が拮抗していたからもれないし、現在のギリシア文明から派生している西欧文明に情報が支配されているからかもしれない。スルタン・マホメットは相当な実力者であると感じるが、彼の世界一の地位と財力を持って、明確な目標に向かって努力しても叶わないこともあるのかもしれないとも感じた。
短くて読みやすいので、ローマ帝国の最後の日に触れたい人におすすめな一冊である。