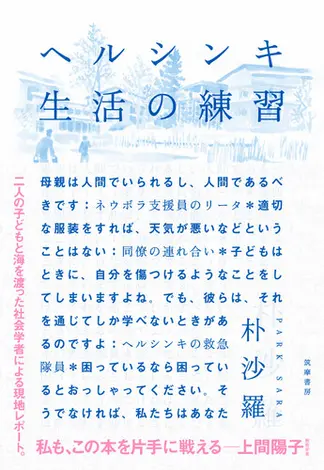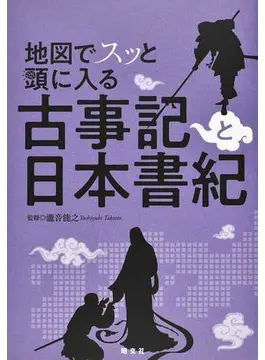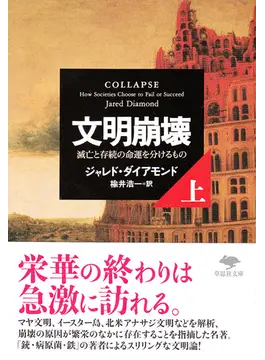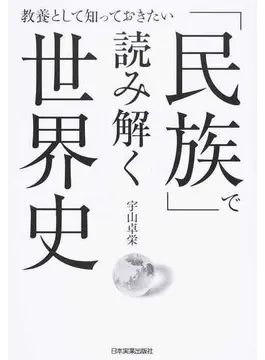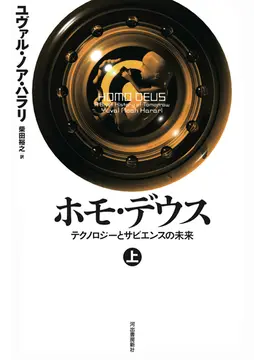2018 河出書房新社 ユヴァル・ノア・ハラリ(著), 柴田裕之(訳) ハラリさんのサピエンス全史の次の作品として気になったので、読んでみた。
本の構成
飢饉と疫病と戦争を乗り越えたホモサピエンスには次の課題が必要だ。1つ目は死を乗り越えること。2つ目は幸福感を我が物にすること。加速する資本主義がもたらす科学の進歩は止められない。マルクスの思想が資本家の行動を変えたように、新しい知識も再帰的に未来を変えるために予測もできない。
第一部では他の動物たちを比較して、共同主観とがホモサピエンスを特別なものにしていると説く。第二部ではホモサピエンスは共同主観によってお金、神、国家、起業を作り、科学でそれを強化してきたと説く。もっと力を得るために人生の意味を捨て、人の自由意思を権威とする自由主義的な人間至上主義を打ち立てた。第三部では自由主義的な人間は自由意志の存在を礎にしているが、自由意志はあるのか?感情を持たないアルゴリズムの方が首尾よく働くし正確で人々は心地よいので、社会システム全体がアルゴリズムやデータによって決定するような方向に変化していくと説明する。
ポイント ー 第一部:ホモサピエンスの特別性
世界の大型動物の重さを比較すると3割が人類、6割が家畜、野生動物は1割。アミニズムでは人間は野生動物の一部だったが、農業革命によって人間が動物たちと話せなくなったアダムとイブの神話があるが、つまり家畜が生まれた。聖書などでは動物たちとの繋がりが廃されて、神を通して人は自然(動物)にアクセスする。農業革命が有神論の宗教を生み出し、神と人間の世界を作り、動物の残酷な利用を正当化した。その次に起こった科学革命は人間至上主義の人間だけの世界を誕生させた。(生物はアルゴリズム。感覚もアルゴリズム、ほとんどの決定をしている。)
人は強力だがそれは豚の命より人の命が尊いことになるか?人間には不滅の魂があって、動物にはないからだと一神教は答えるが、科学的に人間には魂が発見されていない。人間には意識ある心があるからだと答えもある。魂は物語だが、心は主観的経験だ。心は存在理由が分かっていない。感情はなぜあるのか?記憶や創造や思考は結局アルゴリズムではないか。心も発見されていないとすれば、それはエーテルと同じ想像上の産物ではないか?心がなくてもアルゴリズムは目的を達成するので、なくても良いのではないか。では人間以外の動物には心はないのか?ラットにも心はある。チンパンジーも人間と同じように不平等を良しとしなかったりする。ではなぜ人間が優れているのか?それは大規模に協力できるからだ。共同主観とも言える「意味のウェブ」がそれを可能にしている。
ポイント ー 第二部:ホモサピエンスが作った世界
「意味のウェブ」ではどんな物語が語られているか?動物は客観的世界と自分の感覚の世界で暮らしているが、人間にはお金、神、国家、起業の物語の世界もある。ファラオもエルヴィス・プレスリーも何もしていなかったが虚構のシンボルとして存在し、実際の現実を動かした。グーグルなどの企業という虚構も実際の現実を動かしている。貨幣が創造の産物の紙切れだ!と否定するとかなり生きづらいのと同じように十字軍が送られていた頃にキリスト教の聖典や古代エジプトでファラオの神聖を否定して生きるのは難しかった。現代でも紙切れが世界の価値観を作る。紙幣、学位、経典。それらの虚構は評価基準を提示するので、集団の目標も左右する。キリスト教が戦争を起こしたりして人々を苦しめる。現在でもふと気付くと虚構であるはずの国家や貨幣や企業のために人生を犠牲にしていたりする。
科学は虚構に取って代わる普遍的な事実と思う人もいるが、虚構を現実に合わせるために科学は現実を変えることができるので神話と宗教の力を強めた。宗教とは霊性や超自然的な力、神の存在ではなく、変えることができない道徳律の体系に人類が支配されているという。それによって社会秩序を維持して大規模な協力体制を組織するものである。霊的な旅とはそれとは真反対のもので、道徳律から逃れようとする試みのことだ。また科学は幸せや良し悪しなどの人間の行動の判断基準を作るものではない。科学と宗教はどちらも集団的な組織としては、心理より秩序と力を優先する。両者は相性が良い。ということで、人間至上主義の教義は科学理論に取って代わることはない。歴史を通じて、科学は人間至上主義との間の取り決めを形にしていったと見ることができる。
現代人は力と引き換えに人生の意味を捨てる約束をした。過去の虚構の中では人生に意味があったが、その世界観によって人の行動は制限されていた。現代は絶え間ない研究、発明、発見、成長を続けているが、意味もなく結末もない。しかし資本主義は信用経済を通じて経済成長を良いもの、優先すべきものと規定して、家族との絆よりも優先すべきものと価値判断を提供し、宗教の領域にも入ってきている。資本主義のサイクルに終わりはなく「これ以上は成長しなくて良い」とはならない。また原材料とエネルギーには限界があるが、知識に限界はない。北京の大気汚染など成長による不利益を富裕層は新しい方法で回避する。一方で温室効果ガスなどによる被害を貧しい人は回避できない。資本主義には経済破綻や生態系のメルトダウンというリスクはあるが、今の所起こっていない。グローバルな協力によって飢饉や疫病、戦争を抑え込んでいる。しかし競争のストレスが多く、意味のない世界を人間はどうやって生き延びているのか?それが人間史上主義だ。
力を提供してくれる代わりに、人生の意味を与えてくれる宇宙の構想の存在を信じるのをやめる必要がある。意味を失う・神の死は社会の崩壊を招くが、今の所、力を維持しつつ、社会の崩壊を回避している。意味も神も自然の方もない生活への対応策は、人間至上主義が提供してくれた。かつては美や善、真実は人々が決めるものではなく権威が決めるものだった。人間至上主義では人々は自分の欲求に従い行動すればよいが、嫌な思いをする他人がいてはならないというのは規範である。政治は有権者によって決まり、製品は消費者によって判断される。教育も自ら考えることが重視されるようになった。神の世界には何もなくなり、自分の内なる世界が重視されるようになった。中世は知識=聖書x論理だったが、現在は知識=経験x感性だ。
ポイント ー 第三部:ホモサピエンスの苦悩と未来
自由主義の哲学は科学的発見がある。2016年の世界は個人主義、人権、民主主義、自由市場の自由主義のパッケージに支配されている。自由主義が個人を重視するのは人間には自由意志があるという前提があるからだ。一方で現代科学は自由を発見できておらず、選択に携わっているのは決定論とランダム性である。ダーウィンの進化論の前提は人の行動が遺伝子に依るという決定論で自由意志を否定している。また欲望に従うことが自由とされているが、人は自分の欲望を選ぶことはできない。そして研究室では電極でラットの欲望をコントロールできているし、人の脳を電極で刺激して鬱を改善させる実験もされている。
さらに人間の自由意志の選択を権威としている自由主義の脅威は3つある。一つ目は高度なテクノロジーによって今まで必要だった仕事でも人が不要になること。2つ目は決定がアルゴリズムによってなされて、それを人は心地よく感じるようになるので、アルゴリズムが決定する世界になること。3つ目は人が経済力によってアップデートされたエリートと無用の人たちに二分されること。
自由主義が崩壊したらどのようなイデオロギーが子孫の進化を支配するのか。1つ目はテクノ人間至上主義だ。テクノロジーによって人間の心をアップデートして第二の認知革命を起こしホモデウスを生み出す必要性を説く。しかし心の研究範囲は限られていてアメリカ人が大半でネアンデルタール人の感覚や他の哺乳類や生物の感覚なども研究できていない。また人間の感覚をコントロールできたとすれば人間至上主義が拠り所にする意思をコントロールできることになり、矛盾を抱える。
2つ目はデータ至上主義だ。自由市場資本主義と国家統制下共産主義はデータ処理の観点でいうと前者は分散型処理、後者は集中型処理である。政治が世界の変化についてこれないからといって、市場に委ねると市場にとって良いことばかりをするようになり、温暖化やAIの危険への対処を怠る。また人類の発展をプロセッサによる分散処理とその接続というデータ処理の観点で捉えることもできる。データ市場主義者の中には情報の自由を説く人もいる。個人情報の自由はプライバシーの問題があるが、人はSNSを通じてすでに多くのデータを”シェア”している。結婚における伴侶の選択もキャリアの選択も”感情”に依るのでなく、アルゴリズムに依る方がよいのかもしれない。
人は自分の欲望を選ぶことはできないー哲学。電力、人口知能は過去のデータ。非論理的に選択しているかもしれない。
最後
本書にかかれていることは可能性であるという。3つの問いがある。生物は本当にアルゴリズムにすぎないのか?知能が意識から分離しつつあるが、知能と意識のどちらのほうが価値があるのか?高度な知識を備えたアルゴリズムが自分より自分を知る時に社会や政治や日常生活はどうなるか?と締めている。
いろいろ自分の視点からのツッコミができるので面白い。ホモサピエンスの分析では哺乳類との比較をメインにしているが、実は鳥類とか昆虫とかだって共同主観は持っていないかもしれないが重要な地位を占めないのだろうか。将来は知能をもったロボットとの戦争ではなく、カラスとの戦争になるとかだったら面白い。二酸化炭素の話が出てくるが、それも宗教じゃね?また人の自由意思についてスピノザなどがすでに考察している。
ハラリさんはマルクスの予言は偉大で世界を変えたと言っているので、ハラリさんも予言で未来を変えたいのではと思うけど、話がグーグルなどの最近の話なので、10年後に読んだら古めかしい話になっているのかしら。人類の未来について考えてみたい人や、ハラリさんの説にツッコミを入れたい人はおすすめです!