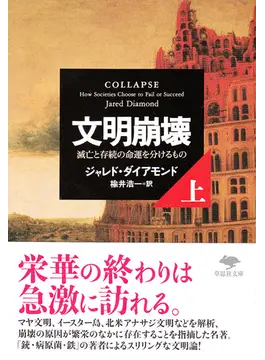
ジャレド・ダイヤモンド氏による「銃、病原菌・鉄」に続く著作であり、様々な文明の崩壊を考察する内容となっている。全体としては現代の環境問題への対応について問題提起をしている内容に読めた。
本の構成
4部16章で成り立っている。文明の崩壊を招く要素として環境被害、気候変動、近隣の敵対集団、有効的な取引相手、環境問題への社会の対応の5つを挙げてこの観点で各文明を分析する。第一部「現代のモンタナ」では過去の鉱業からの汚染と、森林伐採の必要と経済的な効率、古くからの暮らしと土地開発の摩擦について、第二部「過去の社会」ではイースター島での森林資源の不足による崩壊、ピトケアン島・ヘンダーソン島での人口に対する資源不足による崩壊、アメリカのアナサジ族の森林伐採と旱魃による崩壊、マヤの敵と旱魃による崩壊、スカンジナビア半島から外海に進出し移住したヴァイキングの行く末、特にグリーンランドの興亡について、加えてニューギニア・ティコピア・日本の成功例について、第三部「現代の社会」では、ルワンダでの大虐殺の土地問題にまつわる背景、一つの島に隣り合うドミニカとハイチ、中国の人口・食糧・環境問題、痩せた土地を搾取するオーストラリア、第四部「将来に向けて」では、社会がなぜ壊滅的な方向に向かうか、大企業と環境対策の良い事例と悪い事例、十二の環境問題と反論やこれからについて語る。
気になったポイント – 支配者層の非合理
支配者層が無駄なものを浪費したり自分だけ裕福な暮らしをしたりと、非合理的な決定をしていたのが社会が崩壊した原因の一つなのではないか、とあった。イースター島の社会階層やグリーンランドにも社会階層あり、それらによる弊害である。
社会階層は社会のアイデンティティを維持するために必要なものだったのではないかというのが自分の考えである。滅亡した社会にはあったが多くの現存している社会にも存在する。それがないと集団としての物語が失われてしまい、人々が野生化してしまったら、それこそがら文明が崩壊してしまうのではないかとも感じる。
最後に
崩壊した社会は環境が痩せていて人類が適応するのが難しい場所だったという印象で、度重なる旱魃などの環境変化で崩壊するケースもある。その地域がどのくらいの人口を養えるかが重要だったが、現在では地球規模のやりとりで養える人口が変わっている。
その土地が持っている潜在能力が重要だったが、現在の地球はどのくらいの人口を養うことができるのか、興味は膨らむ。過去の文明崩壊や世界の環境問題に興味がある人にはおすすめです!