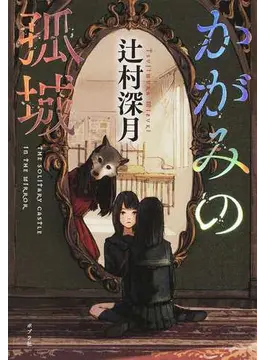若い時に見て感動した作品。娘に見せたくて見てみたが、自分も以前と変わらず感動できた。ただ昔は気づかなかったお父さんの感情に大きく共感できた。
登場人物
時代は1990年代のバブル景気のころ。哲夫は岩手から出てきてアルバイトをして不安定な生活を送っている。父の昭男は妻を亡くし岩手で一人暮らし、哲夫を心配している。征子(せいこ)は鉄工所の得意先である製作所で働く工員だが、聴覚に障害がある。
物語の始まり
東京の居酒屋でアルバイトをしている哲夫は、母の一周忌で帰った故郷の岩手でその不安定な生活を父の昭男に戒められる。その後、哲夫は下町の鉄工所にアルバイトで働くようになるが、製品を配達しに行く取引先で征子という美しい女性に好意を持つが、なかなかきっかけを掴めない。哲夫の想いは募るが、あとから彼女の障害について知る。
テーマ
哲夫は征子の障害を物ともせずにアプローチしていく。一方の征子ははじめは戸惑うが徐々に真摯な想いを理解していく。二人の様子は美しく描かれている。父の昭男は落ち着かない「息子」を心配しているが、結婚を申し込んだと知って驚く。「本当に哲夫でいいのか?」と征子を本気で心配する。心優しく美しい征子が哲夫で良いというのと昭男は嬉しくて眠れなくなってしまう。
以前は障害の困難を乗り越えて共に手を取り合って歩む姿が心に残った。もちろんその姿も変わらず印象的だったが、今回は息子を心配する父と喜ぶ父、極めつけの最後の回想シーンがグッと来た。自分もいつかこのような感情を抱くのであろうかと。
最後に
息子や父の描写の他に、時代の雰囲気の描写が非常に勉強になる。寂れていく農村、地方からの出稼ぎで東京の発展が支えられていたこと。今よりも熱気があった時代。そんな時代描写などは郷愁を感じさせるように描かれてもいるが、実は日本の問題点を描いている気もする。
息子を持つ父親は特に、子を持つ父親は見なくてはいけない名作。広く鑑賞されてほしい作品です。